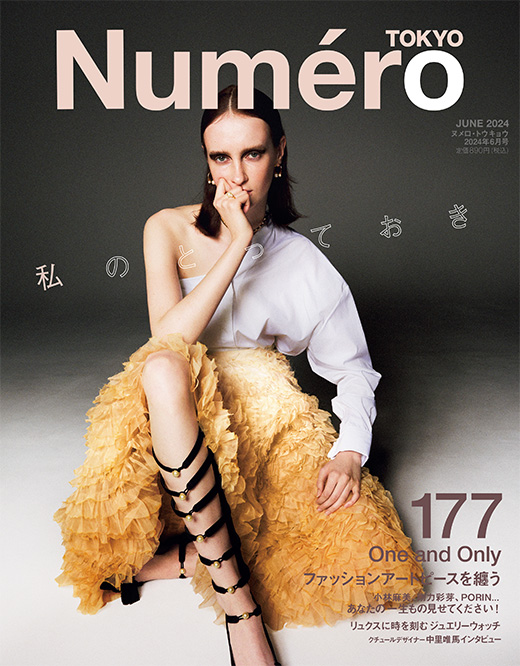原美術館 “最後の展覧会” に込めた想いと新たな展望
1979年の開館以来、日本の現代アートシーンを牽引してきた東京・品川の原美術館。その最後を飾る展覧会「光ー呼吸 時をすくう5人」が開催されている。主任学芸員の言葉をとおして、この場所に刻まれた記憶をたどり、原美術館の次なる一歩を展望する。

モダニズム建築の名美術館、その魅力と軌跡をたどる
江戸の昔から風光明媚な土地として知られた品川・御殿山の閑静な住宅街に、1979(昭和54)年に開館した原美術館。当時の日本ではまだ希少だった現代美術専門の美術館として、我が国の現代アートシーンを半世紀にわたり牽引してきた存在だ。 中庭を囲んで円弧を描くように広がる建物は、実業家・原邦造の邸宅として1938(昭和13)年に建てられたもの。銀座の「和光ビル」などを手がけた建築家の渡辺仁による白亜の洋館は、昭和初期の貴重なモダニズム建築としても名高く、建物と一体化した常設展示作品をはじめ、特色ある鑑賞空間として人気を誇る(※1)。 展示企画としても他に先駆けて世界の現代美術の動向をいち早く紹介し、日本の美術館としては初めて森村泰昌や荒木経惟、ソフィ・カルらの個展を開催、2000年頃からはコンテンポラリーダンスや音楽などのイベントを行うなど、一貫して大きな支持を集めてきた。 (※1)参考リンク:原美術館Web/美術館について
その原美術館だが、現在開催中の展覧会「光ー呼吸 時をすくう5人」(9月19〜2021年1月11日)の会期をもって品川での歴史に幕を下ろすという(※2)。名残を惜しむ声が多く寄せられるなか、本展はこの場所を訪れた人々が時間や空間との対話をとおして、新たな記憶を紡いでいくことのできる展覧会となっている。主任学芸員の坪内雅美に、今回の展示へ込めたメッセージを糸口として、展示空間としての建物の魅力やこれまでの足取り、気になる今後の展望を尋ねた。
(※2)参考記事:「原美術館、最後の展覧会「光―呼吸 時をすくう5人」」

建物/作家5人/鑑賞者、それぞれの時間と向き合う展覧会
──今回の展覧会は、「そこにある時間や空間に光をあて、自身を取り巻く社会の息遣いをかたちにし続けている5人」の展示ということですが、このテーマに込めた意図について教えてください。
「本展はもともと4月開幕の予定で、この建物での最後の展覧会としてはコレクション展を予定していましたが、コロナ禍で休館を余儀なくされたことにより、結果的に9月からの開催となりました。とはいえ、品川での最後の年を飾る展覧会として企画されたものであることに変わりはありません。先行きが不透明な時代のなかで、過ぎ去る時を自らすくい取り、見る人の心に深く語りかける力を持った作家として、今井智己、城戸保、佐藤時啓の3名に加え、コレクションから佐藤雅晴とリー・キットの2名の作品を選びました」

──展覧会のステートメントには、「手に余る世界の情勢に翻弄され、日々のささやかな出来事や感情を記憶する間もなく過ぎ去ってしまいそうな2020年」とありますが、技術の進展が社会全体にかつてない変化や地球規模の問題をもたらすなかで、立ち止まって考えることの重要性は、コロナ禍以前から高まりつつあったように思います。
「そのとおりですね。今回の展示で佐藤時哲さんはこの場所を舞台にした新作を発表していますが、制作は建物の老朽化という“手に余る”状況の中で、ご自身の思い出と向き合いながら行われました。また、リー・キットさんの作品は静謐で詩的な表現の中に、故郷である香港の政治状況という“不穏な情勢”を内包したもの。一方で、城戸保さんの写真は明るくユーモラスながらも、現代社会の主流から遠いところにあるさまざまな物や事象をとらえています。
昨年逝去した佐藤雅晴さんは16年に原美術館で個展を開催していますが、その制作作業はがんの再発という“手に余る”状況と向き合う行為だったといえます。

また、11年の福島第一原子力発電所事故をテーマにした作品を展示している今井智己さんは、あの事故がそれまでの現実や時間の認識を考え直す大きなきっかけになったと語っています。1年先のことも定かではない状況の一方で、廃炉の作業は今も続けられ、数十年先まで続いていくわけですから。このように、それぞれの立場で“手に余る”現在の状況と向き合い、流れ去る時間や空間に光を当てるアーティストたちの息づかいを、展覧会として表現したいと考えました」

“都会の聖域”で紡がれてきた、一期一会の展覧会たち
──そうしたメッセージを発信する場としても、この自然に囲まれた古き良き建物は、“都会のサンクチュアリ(聖域)”とも呼ぶべき空間として機能してきたように思います。
「おっしゃるとおりです。この建物には80年以上の歴史や記憶が内包されていて、そこに作家や来場者がそれぞれに紡いだ時間が散りばめられています。邸宅としてつくられた建物ですから、窓から光が差し込み、鳥の声が響くなど、天気や季節によって印象が刻々と変化します。今回は特に、そうした環境と作品、来場者や作家それぞれの時間や記憶が織りなすような展覧会をイメージしました。
例えば、作家ごとに部屋を区切らず、作品を混在させたのもその一つ。私たちが普段接している世界は、きれいに整理されて存在しているわけではありません。ある場所や出来事の感じ方は、タイミング次第で大きく変わります。この展示にしても、光や温度、湿度などによって時々刻々と見え方が変わっていく。その偶然の出合いともいうべき感覚が、作品の受け取り方に加わってもいいのではないかと考えました。
私自身、約25年にわたってこの場所で展示に携わるなか、空間をどう生かして作品とコラボレーションさせるかということを考え続けてきたので、今回の展覧会は、その集大成といえるものにしたいと思いました。その時々の時間や空間の印象を受けて、体験する人それぞれの中で展示が完成する。まさに“ここでしかできない展覧会”になったのではないかと思います」

──これまでの展覧会を振り返っても、今や巨匠となったアーティストの個展から、新たな視点を提示する企画展まで、そうそうたるラインナップに驚かされます(※3)。そのなかで、建物とのコラボレーションという意味で思い出深い展覧会について教えてください。
「記憶に残る展示は挙げればきりがありませんが、まず思い浮かぶのは「ジム ランビー:アンノウン プレジャーズ」(2008-09年)でしょうか。床一面に特徴的な縞模様を貼り巡らすなど、幾何学的な作品の面白さが建物の形と影響を及ぼし合うよう、一緒に作り上げていって、空間を変容させた展覧会となりました。
「ミヒャエル ボレマンス:アドバンテージ」(2014年)と「エリザベス ペイトン:Still life 静/生」(2017年)は、あえて小さな作品を選び、点々と並べる構成としました。いわゆるホワイトキューブではなく、個人の邸宅だった建物だからこそ、成り立つ企画だったといえると思います。住居だった雰囲気を生かした点では、「小瀬村真実:幻画〜像(イメージ)の表皮」(2018年)。かつて原家で使われていた家具を置くなどして、部屋ごとの空間を構成していきました。

そして、リー・キット「僕らはもっと繊細だった。」(2018年)。リーさんは展示前の作業期間のうち、最初の数日間は光の入り方や影の移ろいなどをはじめ、静かにこの場所を観察して、そこで感じたことを展示として作り上げていきました。その経験があったからこそ、今回の「光ー呼吸 時をすくう5人」の展示が生まれたのだと思います」
(※3)参考リンク:原美術館Web/展覧会リスト

原美術館から「原美術館ARC」へ。その未来を展望する
──この展覧会をもって原美術館は閉館となりますが、あらためてその理由を教えてください。
「理由としては、この建物の老朽化が挙げられます。竣工から80年以上にわたり、改修や増築を重ねてきましたが、これ以上この場所での継続は難しいと、理事長の原俊夫が判断したということです。建物の今後については、現時点ではまだ決まっていません。2021年春からは群馬県渋川市のハラ ミュージアム アークの名称を「原美術館ARC」と改め、活動を継続していくことになります。
ただそもそも原は、“この建物ありき”で美術館の開館を考えていたわけではないのです。現代美術を日本へ普及させたい、美術によって国際交流を図りたいという思いがまずあって、各所で視察をするうちに、自身の祖父が建てたこの邸宅を使おうと思い至ったということですね。それから40年余りが経過し、今や日本でも都市部を中心に、現代アートに触れることのできる場所が数多く営まれるようになりました。それならば今度は都市ではなく、まだ現代アートが少し遠い存在である場所でこそ、この活動を続けていく意義があるのではないか。そのように考えています」

──その一方で、この建物と一体の存在として人気を集めてきた数々の常設展示作品の行方がどうなるのかも気になります。
「もちろん、移設する方向で進めています。浴室だった空間全体を使った奈良美智さんの作品『My Drawing Room』は、空間をほぼ再現する方向で考えていますし、来館者用トイレを作品化した森村泰昌さんのインスタレーション『輪舞(ロンド)』や宮島達男さんの作品『時の連鎖』についても作家と相談を重ねながら、原美術館ARCでの展示の形を検討しているところです」

──この建物における活動は終了となるけれども、今後は拠点を一本化して、新たな展開をしていくということですね。
「そのとおりです。原美術館とハラ ミュージアム アークが一緒になり、原美術館ARCとして活動していきます。なお、ハラ ミュージアム アークは磯崎新の設計によって88年に開館しましたが、コレクションの収蔵庫としても機能しており、約1000点の作品が収められています。現代建築による木造の美術館は珍しいこともあり、建築としても大きな魅力がある場所です。
品川での活動やこの建物を愛してくださったみなさんに感謝しつつ、私個人としては「ここでやるべきことは、ほぼやり尽くした」と感じています。新たなステージへと移行する原美術館の活動をぜひ、より多くの方々にご覧いただければ幸いです」

※掲載情報は12月11日時点のものです。
開館日時など最新情報は公式サイトをチェックしてください。
「光ー呼吸 時をすくう5人」
会期/2020年9月19日(土)〜2021年1月11日(月・祝)
会場/原美術館
住所/東京都品川区北品川4-7-25
開館時間/平日11:00〜16:00、土日祝11:00〜17:00
休館日/月および12月28日〜1月4日 ※1月11日は開館
料金/⼀般¥1,100、大高生¥700、小中生¥500、70歳以上¥550
※原美術館メンバー無料
※学期中の土は小中高生無料
※ウェブサイトからの事前予約制
URL/http://www.haramuseum.or.jp/jp/hara/exhibition/897/
Interview, Text & Edit : Keita Fukasawa