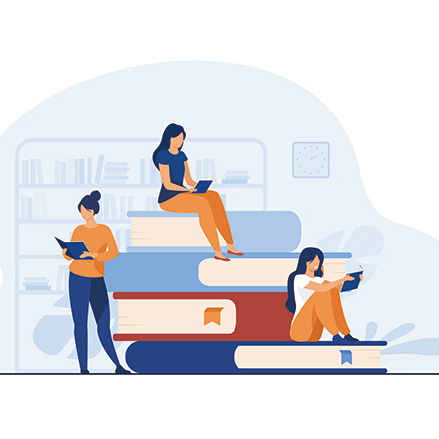金原ひとみインタビュー
「初めてハッピーエンドを書いたという気持ち」
旬な俳優、女優、アーティストやクリエイターが登場し、「ONとOFF」をテーマに自身のクリエイションについて語る連載「Talks」。 vol.22は作家、金原ひとみにインタビュー。

──それが、恵まれた環境のなかでもどこか違和感を覚えている主人公、カナの物語だったわけですね。
「そうですね。世間的には超ダメ人間とされるようなやつを書いてやろうと(笑)。ただ『持たざる者』から感情的に続いている部分はありました。『持たざる者』は、4人の主人公が震災や人間関係のトラブルによって、それぞれに持つ世界を喪失し、そこからどうやって生きていくかという話ですが、新作はその喪失の10年後を描いているような。
たとえば、世界がまっとうな時には思う存分まっとうでない思いや物語を表現できますが、世界がおかしくなると、正気に引き戻されるようなことってありますよね。震災後、社会や世論がおかしなことになって、私はそこの関係がひっくり返ったと感じました。でも、『持たざる者』を書き上げて、ようやくかつての小説に向き合うときの状態に戻れた気がしたんです」
ヒロインが辿りついた幸せの形とは?
──デビュー作の『蛇にピアス』のときから、金原さんの小説には自分が何を求めているかわからず試行錯誤しているヒロインが多い印象があります。今回もそれは共通していると思うのですが、金原さんのなかに核としてあるものなんでしょうか。
「自分自身、これでいいのかなと手探り状態で生きているので、迷いなく生きている人はなかなか書けないですね。『蛇にピアス』では、ヒロインのルイはピアスやタトゥーによって非日常に行くのではなく、むしろそこに日常を感じている。その方がしっくりくるんです。私も、煮詰まっている時にピアスを開けに行って「あー落ち着いた」と思ったことがありました。
今回のカナにしても、ストーカー化した元恋人に殺されかける事件に遭いながらも、まっとうな生活を築き上げてきたなかで、同時にその生活への違和感と、別の方向へのベクトルを持ち合わせています。そんなふうに引き裂かれていく感覚というのは、誰しも多少はあるんじゃないかと思うんです」
──いざ幸福が目の前にあると怖くなる、というような?
「というよりも、今の世の中にはびこる“これこそが幸せ”というビジョンが嘘っぽく感じるんです。たとえば、結婚して子どもがいてマイホームを持ってというような、すでに形骸化した幸せのイメージが今でも横行しているのも不思議に思えます。ルイもカナも、言ってみればその形骸化した幸福ではない、それぞれの幸福を追求しているだけだと思います」
──ラストで彼女がひとつの決断を下す姿には、希望を感じました。
「迷いの中で受動的に生きてきた彼女が、何かひとつ掴んでみようと思った瞬間だと思います。それまで自分が疑いを抱きながらも無理やり信じてきた世界を捨てる覚悟をして、一歩踏み出したということなのだと思います。ゲスな道を選んだと思う読者もいるかもしれませんが(笑)、私自身は初めてハッピーエンドを書いたという気持ちがあります」
──金原さんの小説には帰国子女もよく登場しますが、小学校6年のときにサンフランシスコに1年いらっしゃった経験が影響していますか。
「そうですね。アメリカに行ったとき、とても開放感があったんです。日本での決められた枠組みが外の世界では通用せず、まったく違う考えを持つ人たちがいるのが当然、というのが新鮮でした。特にサンフランシスコは多文化だし、いろいろなことに寛容でのんびりした雰囲気でした。その分、日本に帰ってきたときはすごく辛かったんですけど(笑)。でも、いま自分が信じている価値観というのは一歩外に出たら通用しないということを、身をもって体験できたのは大きかったと思います。思春期って、狭い世界の中でこっちもあっちもだめだと感じてしまう。でもそういうときに、こういう道も、あるいはああいう道もあるんだという風に考えられるのは、強みになりますよね。狭い枠組みの中でもがいている人よりも、広い枠組みの中でもがいている人を書いていきたい、という気持ちは常に持っています」
──映画もお好きとうかがいましたが、最近、印象に残った映画や本はありますか。
「映画は、最近ではグザヴィエ・ドランの作品が好きです。あと、ラース・フォン・トリアの『メランコリア』は、観ている間の半分ぐらいは号泣していました。彼の作品に出てくる女性の苦痛のかわし方というか、処し方が本当に美しくて、あらゆるシーンに見惚れてしまいます。小説だと、トルコ人作家のオルハン・パムクの『無垢の博物館』がすごく良かったです。ある男性が、思いを寄せる女性のものをどんどんコレクションしていくという話で、過激な表現はいっさいなくて、正直上巻は読んでいてだるかったのですが、終盤に向かって血の気が引いていくような面白さでした。下巻の後半は、本当にぐるんぐるんと世界がめくれていくような体験で、この歳になって読書でこんな思いをすることになるとは、という感激と共に読み終えました」
パリの女性は自分の存在に自信を持っている
──ところで、金原さんはオンとオフの状態の差は大きい方ですか。
「いえ、あまり違いがないような気がしますね(笑)」
──執筆をされていないときの、ストレス解消法などは?
「最近、時間ができると一人黙々と、腹筋や腕立てなど筋トレをしています」
──毎日の決まったリズムなどはありますか。
「今は完全に夜型で、子どもたちが寝た後10時ぐらいからメールや細かい仕事をして、それを終えてから朝の5時ぐらいまで原稿を書き、その後お昼まで寝ています。朝は夫が子どもたちを学校に送るので、子どもたちには朝は何があっても絶対にママを起こしちゃ駄目だよと吹き込んでいるんです(笑)。お迎えが四時半なので、それまでがフリータイムですね」
──『マザーズ』では子育てをする母親たちの本音を書かれていましたね。フランスではわりと早くから子どもを保育園に預けるのが常ですが、日本の子育てとの違いを感じますか。
「日本では母親たちに対して『お母さんなのに…』というような無言の抑圧がありますが、フランスでは本当に皆無なので、その辺の葛藤はなくなりましたね。なので、もしこっちで出産していたら『マザーズ』は書けなかったと思います。日本では今、女性にとって子どもを持つか持たないかというのはすごく大きな選択になっていますが、フランスだともっと気軽というか、妊娠、出産が自然の流れの中にある気がします」
──フランスに来て、ご自身のなかではどんなところが変わったと思いますか。
「いろいろ変わりましたね。自分に似合うと思うものも変わって、ファッションもシンプルになったし、ハイブランドのお店にはほとんど行かなくなりました。日本にいたときに凝り固まっていた部分がフラットになって、自由に何をやってもいいんだと思えるようになった。特に、パリに来て最初の1、2年は刺激が強かったです」
──たとえばどんな点が?
「男女の境があまりないところでしょうか。女性が媚びないし、媚びない自分に自信を持っている。フランスの、特にパリの女性はものすごく無愛想で、一部の人を除けばファッションにもかなり無頓着なんですが、それぞれが自分の存在に自信を持っているんです。自分の思いや感情をとても大切にしていて、わがままだなと感じることも多々ありますが、空気や人の顔色を読み過ぎてしまう日本人と足して二で割ればちょうどいいかもなー、と思ったりします」
Photos:Masaru Mizushima
Interview & Text:Kuriko Sato
Edit:Yuko Fukui
Profile