ザ・ジャパニーズ・ハウスにインタビュー「いつだって最後には必ず終わりがやってくる」by Natsuki Kato
インディーロックバンド、ルビー・スパークスのブレーンとしてはもちろん、音楽への愛と知識に溢れた“音楽オタク”としても知られるNatsuki Katoが、気になるアーティストに独自の視点で取材し、自らの言葉で綴る不定期連載。第3回はソロプロジェクト、ザ・ジャパニーズ・ハウス(The Japanese House)としてセカンドアルバム『イン・ジ・エンド・イット・オールウェイズ・ダズ(In the End It Always Does)』をリリースした、シンガーソングライターのアンバー・ベインにリモートでインタビューを行った。

前作から4年、パンデミックによる閉鎖的でループされた日々を経て、信頼を寄せる才能ある仲間たちとともに再びオープンにポップスを奏でる『イン・ジ・エンド・イット・オールウェイズ・ダズ』。タイトルやリリック、カバーアートのサークルに示された、「どんなことが起きても最後にはきっとなんとかなる」というどこか哀愁があり同時にポジティブなメッセージがこの現代に響く。アンバーの親しみやすい人柄、フラットな思考、そして想像以上に軽快なトークから、ザ・ジャパニーズ・ハウスの音楽が多くの人々やアーティストを惹きつける魅力を探った。
良い感情だけでなく、悪い感情も感じることが大切
──約4年ぶりのアルバムとなりますが、この4年間で世界はパンデミックなどを含めさまざまなことが変わりました。アンバー自身の周りではどのような変化がありましたか。
「パンデミックの前は来る年も来る年も、生活の大半をツアーに出て過ごしていたんだけど、そこに突如として静かな日々が訪れて。毎日どこかからまた違う場所へ移動するツアーを中心とした、今思えば少し奇妙なライフスタイルから、国内での日常に戻ったんだ。その間に街を出てより海側に引っ越しもしたし、多くの人にとっても静かな毎日が繰り返されるようになったと思う。
その他にも、アルバムの最後の楽曲『One for sorrow, two for Joni Jones』にも登場する、ジョニ・ジョーンズと名付けた犬を飼い始めたり、ある人と交際中でもあった。でもちょうどアルバムを作り終えたときに、その関係にも終止符が打たれて、また街に戻ることになったんだ。まさに今回のアルバムタイトルやカバーのように大きなサークルの中を周って来たような感覚だったよ」
──アルバムタイトルには、ポジティブでありながら同時にネガティヴな意味合いも感じられます。今作には主にどんなテーマがあるのですか?
「”In the End It Always Does”は、基本的には文字通り『すべての物事はいつだって最後には必ず終わりがやってくる』という意味なんだけど、同時に誰かが何かの終わりへと向かうとき、最後にはきっとなんとかなる、という意味も込められているんだ。それからこの言葉はとある映画からの引用でもあって、父がいつもこの台詞を使っていたんだけど、なんて映画かわかる? ダメだ、映画の名前をまったく思い出せない(笑)。でもそれは『何でも最後にはどうにかなる、もしならなかったとしたらそれはまだ終わってないということだ』といった内容で、父から本当によく言われた台詞だったんだ」
──とても素敵な話ですね。
「時には物事は終わる。でも私が今までに学んだ最高のことは、結末が必ずしも悲しいことである必要はないってこと。何かの結末を受け入れることはとても大切だと思う。『Sunshine Baby』でもヴァースの一箇所でアルバムタイトルを歌ってる。
“To be putting off the end
cause in the end, it always does”
(終わりを先送りにしたって
だって結局いつだってそうだから)
ってね。
あと
“Everything is cyclical
Hold on to this feeling cause you won’t feel it for long
You won’t feel it for long”
(全てが周期的
この感覚を持ち続けよう、長くは感じないだろうから
長く感じることはない)
という歌詞があるんだけど、これは映画『君の名前で僕を呼んで』からの引用なんだ。父親が主人公である息子エリオに、悲しみがあっても、それを消し去ってはいけない、そうしないと40歳になって何も感じなくなる、というような内容を語りかけているシーンがあって。この引用は、完全にその台詞からの使いまわしのようなものだけど、要はそういうことを感じているときは、良い感情だけでなく、悪い感情も感じることが大切だということなんだと思う。なぜなら誰だって関係は長く続くわけではないんだから。何かを感じるということは、とても素晴らしいことだよ。難しい感情的なことを対処するときに、とても助けになるからね」
私的な視点で身の回りのクィアな人間関係を描く
──僕自身も作詞をする際、映画や物語からインスピレーションを受けて架空のストーリーを俯瞰的に描くことが多いのですが、本作の歌詞にはより主観的な視点も感じます。同時にその内向的な歌詞がミニマルなサウンドと見事にマッチしていると思います。パーソナルな経験や思考を歌詞に表現することはあなたにとってどんな意義がありますか?
「客観的に作詞することも好きだよ。というのも、ちゃんと机の前に座って、『よし、このことについてこの曲に書こう』みたいに思ったことはないんだ。でも、インスピレーションを受けたものからメロディーを探して、歌詞を書き上げるまでのプロセスは、ただなんというか、思いつきって感じで、潜在意識のようなところから来ているんだよね。
でも変な話だけど、歌詞を書いているときはまったく意味がわからなくても、それが後々自分の身に起こったり、このことについて書いていたんだと後から気づいたりする、セラピーのようにね。曲作りをしていると、自分が本当は何を考えているのかがよくわかる。自分自身に向けて声に出して考えたりすることは、自分の潜在意識を明らかにするためのプロセスでもある。
政治的な内容や、他人の話を書いたりしているわけではなくて、私的な視点で身の回りのクィアな人間関係を語ることが大事だと思ってる。実際そういう人たちが自分の周りにとても多いからね」
──歌詞の中の情景描写がどれも繊細で、映画のハイライトのように全ての場面、感情が聴き手の頭の中にもリアルに浮かび上がってきます。あなたの過去の思い出や感情を歌詞に書き起こし、歌うことは、あなたにどんな影響を与えていますか?
「ありがとう、映画に例えてくれるのは嬉しいよ。ザ・ジャパニーズ・ハウスと名付けたのも、バンドの名前じゃなくて映画のように表現したかったからなんだ。そもそもは自分の身に起こったことを基にした『ザ・ジャパニーズ・ハウス』というタイトルの映画のアイデアがあったんだけど、自分は映画監督じゃないし、もちろん製作できなかった。だからそのまま音楽のプロジェクト名に使うことにしたんだ。今でも映画への楽曲提供や書き下ろしにもとても興味があるから、数年以内に実現できたらいいなと思ってる。
結局のところ、自分の身の回りに実際に起こったとても具体的でパーソナルな出来事について、かなり深いところまで掘り下げて、踏み込んで語ったり歌ったりすることが、ある意味一番面白いんだと思う。それをインターネット上にアップして、世界中の誰もが聴けるようになってるのはちょっとクレイジーなことだけど、同時に素敵なことでもあると思う。
入り組んだところや、細かなディテールはそれぞれ違うけれど、最終的に核となるのは誰かを好きになったり、失恋したり、といった誰もが経験したことがあるような共感できる感情のことだからね。ギリシャ人哲学者のセネカっていう人が言ってたんだけど、人間が持っている飢え、欲、愛、忠誠心といった感情は、基本的には犬が持っているものと同じだそう。愛や人間関係についてのほうが自分にとっても題材として描きやすいんだ」
人間が繰り返し演奏したものにしか出せないサウンドがある
──今度は本作のサウンド面について話を聞きたいのですが、今作にはレーベルメイトでもあるThe 1975のマシューとジョージがプロデューサーとして参加していますね。
「そう、あとプロデューサーのクロエ・クレイマーのことも忘れないでね(笑)」
──もちろんです。
「メイン・プロデューサーはクロエだったんだけど、ジョージとマシューもみんなで一緒になって取り組んだ。スタジオが全くの異空間のようで、とても良い経験だった。ジョージとはこれまでもずっと一緒に仕事をしてきたから、彼はザ・ジャパニーズ・ハウスの一部であり、不可欠な存在だと感じている。そこへクロエが新たに参加したことで、スタジオでのあり方や作業の進め方について、自分たちの視点を全部変えてくれたんだ。すごいことだよ」
──全体を通してThe 1975の最新作とも通ずる打ち込みの電子音とアコーステックな生楽器によるオーケストレーションの組み合わせが印象的でした。プロデューサーたちは楽曲にどのような変化を与えましたか。
「前作でも実はすでに生楽器の録音も多かったんだよ。いつも生演奏の側面をとても楽しんでるし、新たな演奏技術を学ぶのも好きなんだ。パンデミックの間にも下手くそだったピアノの練習をして、今ではかなりうまく弾けるようになったよ。チューニングの仕方も覚えたし、ギターを覚えたときのように異なるスキルを学ぶことにこだわってる。
それからクロエはヴァイオリンでとても素晴らしい演奏ができることに気がついて、それもミックスした。今作ではほぼ全曲にストリングスが入っているんだけど、それは単純にクロエのヴァイオリンがすごく良かったからなんだ。ジョージはとんでもない技術のドラマーだし、参加してもらった友達のドラマー、フレディ・シェードもとても上手。マシューと私はギターが得意だし、サックスを演奏できる友達もいるんだ。
こういった素晴らしいミュージシャンが周りに多くて、彼ら全員に参加してもらえばいいじゃんって。どんな楽器でも最高のサウンドを見つけることができるし、生楽器では嬉しいアクシデントも起きるよね。ちょっと変なミステイクでも、サンプリングして部分的に活用するとその楽曲を構成する大事な一部分になったりする」
──確かに、僕もよくミステイクをそのままレコーディングしたりしますね。
「打ち込みのようなすでにある音源サンプルだけに頼るのはつまらない。人間が繰り返し演奏したものにしか出せないサウンドがあるよね。誰しもがギターやヴァイオリンなどの生楽器で作曲できるわけではないから、何かスペシャルな物が生まれると思う」
──アンバーの言う通り、今の時代はコンピューターを使えば誰でも色んな音を作り出すことができるようになっていますよね。でもだからこそ、アコースティックギターのような生の楽器は、人の温かみや安らぎを与えてくれると思います。アコースティックなサウンドが光る作品として、例えばボン・イヴェールの『For Emma, Forever Ago』はいつ聴いても自分を落ち着かせてくれます。ボン・イヴェールことジャスティン・ヴァーノンも今作に参加しているんですか?
「彼の音楽はいつ聴いても心が和むよね。厳密に言うと彼はアルバムのレコーディングに参加したわけではなくて、コード進行など作曲部分で手助けしてくれたんだ。彼とプロデューサーのBJバートンが鍵盤パートを書いて送ってくれて、それを曲の中で使わせてもらった。だからジャスティン・ヴァーノンが参加してるって言ったら嘘になるかも(笑)。でも以前も彼とは『Dionne』という曲で共演していて、本当に素晴らしい経験をさせてもらった。私も昔から彼の大ファンだからね」
ライブでみんなが一緒に歌ってくれる瞬間が楽しみ
──一方で、今までアートワークに多かった写真から打って変わって、シンプルにデザインされた今回のアルバム・アートワークはどのようなコンセプトですか。
「アルバム・タイトルが循環を意味するような文章だから、サークル(円形)がシンプルでかつ物事が繰り返されるモチーフとしてぴったりだったんだ。撮影時の写真を使ってみたり、いろいろ試したんだけど、どうもしっくりこなかった。『Boyfood』の写真は楽曲には完璧にマッチしたんだけど、このアルバムにはさまざまな音、好きなもの、感情が詰まっていて、写真のような一枚の画像ではその感覚を表現できないんだ。でもサークルはそういった表現をするのに簡潔的で十分だった。それに、アートや視覚的なものに関しては、とてもミニマルなものに惹かれるんだよね」
──僕はファッションもその音楽性や人柄を視覚的に表現する一つの重要な方法だと思っていますが、あなたの無地のTシャツにデニム、などシンプルな服装も音楽性ともマッチした個性のように感じます。常にありのままの自然体でいるように見えるあなたにとって、音楽をプレイするときのスタイルに何かこだわりなどはありますか?
「ツアーでプレイしているときに自分のスタイルがどうなっているのかは正直よくわからないんだ。ただ、自分が何を着ているかは考えたくない。自分の皮膚や毛のように、自分が一番着心地のいいものを着ていたいんだ。基本はカジュアルなもの、でも毎晩スーツを着て演奏していた時期もあったよ。スーツを着ることで、何か特別な日のような気分になれるのは素敵なことだと思う。でも、自分が今何を着たいのか、何を着たいのかを考えるのは楽しいよ、衣装もライブにおいての一つの大きな要素だからね」
──最後に、このアルバムがリリースされる瞬間、あなたはどんな感情に包まれると思いますか。
「なんだろう、とにかくこのアルバムをリリースできてとても幸せだよ。みんなに聴いてもらえるのが本当に楽しみ。作品が良いか悪いか言われるのを待っているような、緊張している感じではなくて、ちょっと準備体操をして待っているような感覚。人々の反応やコメントはインターネットでも見れるし、それももちろん楽しみなんだけど、いつも大きな衝撃を受ける瞬間は、新曲を初めてライブで演奏してそれをみんなが一緒に歌ってくれたりするときなんだ。いつだって驚かされるけど、その瞬間がとても楽しみ」
──ありがとうございました。日本でライブが見れる日を楽しみにしています。
「こちらこそ日本で演奏するのが楽しみだよ」
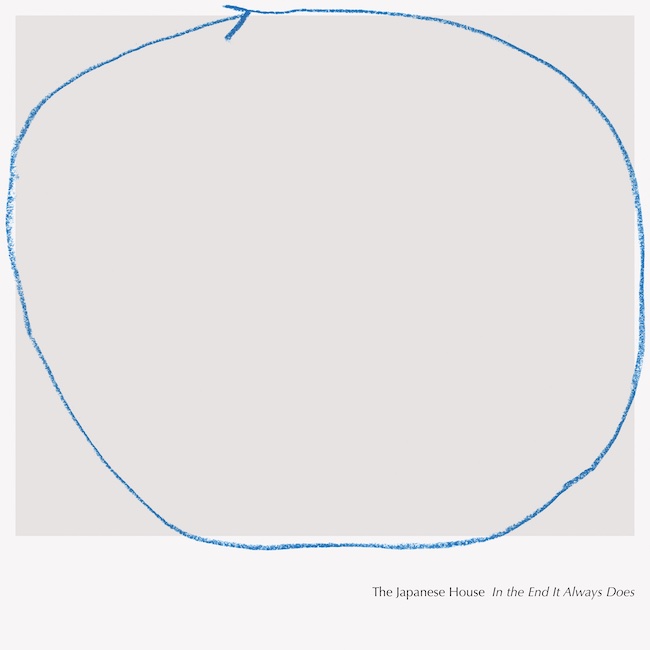
ザ・ジャパニーズ・ハウス
『イン・ジ・エンド・イット・オールウェイズ・ダズ』
発売日/2023年6月30日(金) 世界同時発売
レーベル/ダーティ・ヒット
価格/¥2,750
ストリーミングリンク/lnkfi.re/BCwl0p7v
日本オフィシャルHP/www.virginmusic.jp/the-japanese-house
2024年1月に来日公演が開催決定!
日程/1月15日(月) 梅田クラブクアトロ
1月17日(水)渋谷クラブクアトロ
1月18日(木) 渋谷クラブクアトロ
時間/各回OPEN 18:00 START 19:00
料金/オールスタンディング¥6,500(税込/別途1 ドリンク)※未就学児入場不可
チケット/
◎プレイガイド先行:7月6日(木)~
◎一般発売日7月29 日(土)~
問/【東京公演】クリエイティブマン03-3499-6669
【大阪公演】梅田クラブクアトロ 06-6311-8111
URL/https://www.creativeman.co.jp/event/the-japanese-house/
制作・招聘:クリエイティブマン
Interview & Text:Natsuki Kato Edit:Mariko Kimbara
Profile










