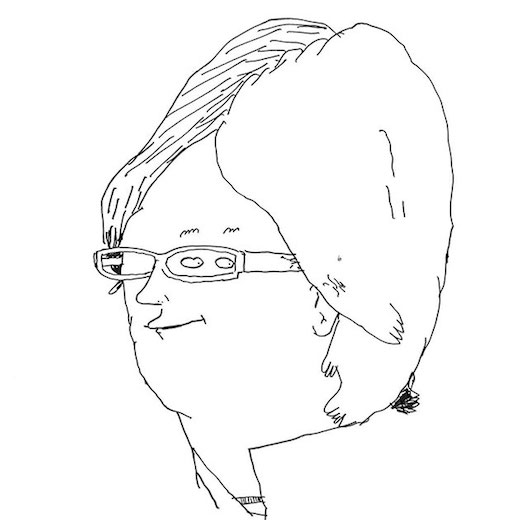編集部が選ぶ今月の一冊|岩川ありさ著『養生する言葉』
あまたある新刊本の中からヌメロ・トウキョウがとっておきをご紹介。今月は、岩川ありさのエッセイを山口博之(good and son)がレビュー。
『養生する言葉』
著者/岩川ありさ  価格/¥1,760 発行/講談社
価格/¥1,760 発行/講談社
言葉があるから生きていける
耳にイヤホンをして音楽を流しながらこの原稿を書こうとしていたのだが、どうしても書き進めることができなった。おそらく何かをしながらこの本のことを考え、書くことはできないと、自分自身でブレーキをかけたのだと思う。 この本の「はじまり」はこんな言葉からはじまる。
“私はいつも死にたかった。だから、生きるために必要な言葉を探しつづけてきた”(引用)
著者の岩川ありさは、現代日本文学の研究者でフェミニズム、クィア批評を通して物語とトラウマについて研究をしている。自身トランスジェンダーであり、子どもの頃に性暴力被害を受けたサバイバーで、それによるトラウマを抱え続けてきた人でもある。本書は、著者が研究者として出会い、読んできた本のなかの言葉や物語が、いかに彼女を支え、自分自身の物語を見つけるきっかけとなっていったのかを記していく本だ。タイトルの”養生する”とは、言葉が生の支えとなってきたということ。
“養生という言葉を私は自分自身の生を養うさまざまな物語とつなげて考えてきた。ちょこんと横に置いて、ヒントとなる物語。自分の感情を教えてくれたり、生きる力を与えてくれるような表現。それらを養生する言葉として捉えてきた。養生する言葉は、生きるための知恵であり、私よりも先に生きてきた人たち、同時代に生きている人たちが重ねてきた、輝くような実践の集積である”(引用)
言葉を通して自分をケアし、自分の輪郭に寄り添うような物語を編むこと。本はただの物質をいうのではない。多様な他者の声の器であり、読むという行為は本の中の言葉と読み手の対話だ。読む人は、他者の言葉を読みながら何かを感じ、考え、言葉にしていく。ゆっくりと話し(書き)、しっかりと聴き(読み)、対話すること、話し合うこと。
“あなたが他人で、私にはどうしようもないことがあるとき、私は私の価値判断の基準を見直すだろう。私は苦しみながら自分を変えてゆく。届かない言葉が届く。それはいつも喜びに満ちているわけではない。それでも回路を閉ざさないでいるにはどうしたらいいのか考える”(引用)
ある経験が自分を縛り、他者に怯えてしまう。どうしてもこの人はこういう人である、こういう経験をした人なのだから、こうであると括られてしまう。記号化され、矮小化され、個人という自分自身を生きたいというシンプルな願いが難しい。それは自分に対してだけでなく、自分から他者に対してであっても同じことは起こり得る。わかりあうことの困難を抱えた他者同士、それでもなおいかにして共に生きていくか、この本はそれをずっと言い続ける。
“傷を持った者どうしすぐにわかりあえると束ねるよりも、違う人生を生きてきた人どうしがゆっくりと話せるような場所が増える方がよほどよい。自分でも認めがたい傷、それでも一緒にいる傷が誰かに伝わるのはとても怖い。否定されるかもしれない。知られることが苦しい。この葛藤まで含めて他者と一緒にいられないか。傷の語れなさについて私は語りあってみたい”(引用)
傷をないものにもせず、傷を直視せよと強要もせず、聴きながら、書きながら、他者と共にいながら傷とも共にいる。それでも他者を諦めない。岩川はそうした姿勢や生き方をたくさんの言葉から受け取ってきたのだ。
”養生する言葉”はトラウマにだけ効くのでない。ぼんはりとした孤独、ちょっとしたつまずきや、日々のもやもやであっても効いてくる。「物語は、自分の生を規定しようとする力に抗い、自分を支配する物語をときほぐす働きも持っている」のであり、他者の物語を通して、自分の物語を編み直すことができるのだ。速さと効率と正解が求められるいま、本書は本を読むという経験の意味を改めて誠実に教えてくれている。
Text:Hiroyuki Yamaguchi Edit:Sayaka Ito
Profile