木竜麻生インタビュー「自分のことを自分がいちばん信じていたい」

1923年、関東大震災の5日後に起こった『福田村事件』は、千葉県の福田村に住む自警団を含む100人以上の村人たちにより、香川から訪れた薬売りの行商団15人の内、幼児や妊婦を含む9人が殺された事件だ。これまで歴史の闇に葬られていたこの史実を森達也監督が映画化。目撃したことを正確に伝えようと奮闘する新聞記者役の木竜麻生に、本作への思いを聞いた。
“正しさ”が暴力的にならないように演じる

──『福田村事件』は、ドキュメンタリー監督で知られる森達也さんが初めて手がけた劇映画ですが、いつもの現場とは違った発見などありましたか?
「演出に大きな違いはなかったのですが、『劇映画を監督するのは初めてですし、至らないところがあるかもしれないので、思ったことや気になることはどんどん聞いてください』と、ご本人がすべてのキャストの方に丁寧にお声がけをされていたのが印象的でした。これまで映画をつくってきた監督でも新しいことに挑戦されているんだという姿勢は、演出にも表れているのかなと撮影現場で思っていました」
──ドキュメンタリーではなくフィクション映画であることの意味をどのように感じましたか?
「私も勉強不足で福田村事件については知らなかったのですが、いざ制作するとなったときに、実際に起こった出来事を関東大震災から100年目の9月1日という節目のタイミングで公開するということもあって、ありのままにストレートに伝えてしまうと受け入れがたい世代もいるかもしれないと思いました。いわゆる、色の濃い映画として捉えてしまう人もいるのかなと。だからこそ、この作品がそこにいた一人ひとりの人物像を描く物語にしたうえで、実際にあったことを織り混ぜる劇映画であることが、広い世代に受け入れてもらういい形だと考えました。私自身、映画で初めて知った出来事が気になって後から調べ、深く知るきっかけをもらうことが多かったので、より深く伝えるために物語を当てているのだ、ということをみんなが意識してつくっていたように思います」
──若手の新聞記者・恩田楓というキャラクターを演じるうえで、特に意識されたことは?
「どの立場で見るかにもよりますが、本人の中で揺れがあったとしても、正論らしい言葉を真っ直ぐに投げる、素直な役柄だったので、正しいことを言うときにあまり暴力的にならないように、とそれだけは意識していました。もちろん、本人はきれいごとを言っているつもりはなくても、観ている人がそう感じてしまったら、すごくもったいないと思って。彼女が新聞記者として意識的に正しい方向へハンドルを切っていたこと。それとは別に、戸惑ったり、怒ったり、悲しんでいたりしたことを内包した状態で演じないと、周りの人からすると、正しさが強すぎるというか、ある種、暴力的に見えてしまうかもしれないと考えました」

──記者という役柄を演じて、情報と向き合うことへの考えに変化はありましたか?
「記者の役柄を短い期間で演じただけなので、実際に責任を持って仕事をしている記者の方の感覚にどこまで近づけたかはわかりませんが、情報を出す側もあくまで人なのだなと実感しました。記者は、可能な限り客観性を持たせて、受け取る人たちがそれぞれの考えに及ぶように、取捨選択できるかたちで情報を出すことを意識しなくてはいけない。でも、主観がゼロになるということはないのだなと。映画も含め、人がつくったものは全部そうとはわかってはいたけれど、あらためて実感したというか。記者としての思い、考え、主観もあって、みんなそれぞれ違う感覚を持っている中で、平等にひとつの情報を渡す行為だからこそ、記事は一人でつくるものじゃないのだと、新聞社がひとつではない理由もつながっているなと思いました。絶対的な客観もなければ、絶対に正しい主観もないし、だからこそ受け取る側も、『これが正しい』という受け取り方をする必要はなくて、好きも嫌いも表を読むも裏を読むも、別の記事と比べるも自分で決めていい。受け取る側として、積極的にそうやっていきたいと思うようになりました」
──客観視したうえで、自分で決めることは大事ですよね。
「結局、あらゆる表現に対して、正しい正しくないを判断することはすごく難しいとあらためて思ったんですよね。そうすることへの責任も意識しましたし。でも同じだけ、受け取る側としても出す側としても、面白がる感覚をなくしてはいけないなと。福田村事件は実際にあった出来事なので、野放しに『面白い』とは言いづらいかもしれないですが、あくまで映画なので、観た後に『面白かった』と言ってもらえることは純粋にうれしいですし、重たいテーマだから真面目な感想を持たないといけないとも考えていないので、観た人の中に何が生まれるかは自由ですが、ただ素直に自分の中に生まれたものを確かめて、それを感じることをしてもらえたらなと思います」
──登場人物の描写も多面的で、簡単にいい人、悪い人とは片付けられないですし、観ながら、自分は絶対そんなことはしない、とは言えないという気持ちになりました。
「私もすごく多面的だと思いましたし、全否定はできない感覚が詰まっている映画ですよね。集団でも、村人、行商、社会主義、新聞社など属する環境によって立場が異なり、その中でも考え方が違う人がたくさんいる。それとは別に、それぞれ生活があったり、夫婦間の問題があったりする。その状況は、たぶん、観客のみなさんも同じだと思うんです。映画としてフォーカスしたときに、それぞれの多様な面が浮かび上がってくるのが映画の面白いところだと思うので」
今も大事にしている大先輩からの言葉

──役者さんも、伝える仕事と言えると思いますが、作品が与える影響についてはどんなふうに捉えていますか?
「監督や作品によって役へのアプローチは変わるものですし、今回のように自分から距離を置いて役を見て、すり合わせていく場合もあれば、自分と役との境界線を限りなく薄くしていくものもあります。自分が演じた役が何かしらの影響を与えてしまうかもしれないということについては、誤解を恐れず言えば、究極、ほとんど考えていません。もちろん、演じた役がどう受けとめられてもその責任は全部負うつもりで、混じりけなく脚本を見て、役に取りかかっています。が、周りへの影響という可能性を探り出すと、私は小心者なので、どんどん身動きが取れなくなってしまう気がして。普段の生活だと、傷つけたくない人たちがいるので、裏切らないように、行動や言葉を選択しながら生きていますが、本当はもっと何も考えずに笑ったり、怒ったり、しゃべったり、わめいたり、思いっきり遠くに行きたいと思っている私が自分の中にいるのも確かで。だから、用意、スタートからカットまでの間だけは、そういう自分を許しています。その分、観ていただいた方の感想は、きちんと全部受け取ってそれを持って次に行きたいなと。そうできるように、もっと度胸をつけていきたいですね」
──出演作品は、どのように選び、決めているのでしょうか?
「社長と一対一で話し合いながら、どちらかと言えば、とてもわがままに選ばせてもらっていると思います。基本的に、純粋に面白いと思えたり、ワクワクできたり、その役を自分にやってほしいという愛情を受け取れるものはやりたいなという気持ちです。
22、23歳の頃、『鈴木家の嘘』という作品で、岸辺一徳さんとご一緒させていただいたときにもらった言葉があって。当時はわかることもあったし、腹落ちしきれずに受け取っていたところもありましたが、自分が年齢を重ねていくうちに、体感としてわかるようになってきたんですよね」
──どんな言葉だったんですか?
「今の木竜さんは、たぶん、スポンジのような状態で、何でも吸収できてしまうから、しすぎてしまうんだよねと。そうなると、人から求められることに答えようとして、一生懸命何をすべきか考えると思うけれど、どこかでつらくなったり、自分がわからなくなったりするタイミングが来るかもしれない。だから、今のうちから、自分が何が好きで、何を楽しいと思って、何を良しとするかを、すぐには見つけられないかもしれないけど、見つけていけるように、自分の生活を大事にするといい。焦ってしまう気持ちもあるかもしれないけど、あまり急ぎすぎないでほしいと」

──なんとも素晴らしいアドバイスですね。
「そうなんです。なので、大前提として、機会をいただけることがうれしいので、全てやりたいと思うところにブレーキをかけて、自分が責任を持って楽しめるか、ワクワクしながらつくれるかを、その都度問いながら選んでいますね。後から、後悔することもありますし、逆にやると決めたのに急に弱気になることもあるんですけどね(笑)。ただ、自分のことを自分がいちばん信じられるようにいようというのは、お仕事をやり始めてからずっと課題にしていて。自分のことも相手のことも同じだけ信じられたら、すごく幸せだなと思いつつも、まだしきれていない部分もあるので、まだまだだなと(笑)。道は果てしないですが、先を走っている先輩方のことを思えば、またご一緒するために頑張ろうという気持ちになります」
──現在、29歳ですが、30代を前にして今までよりも楽になったと感じますか?
「生きづらさの厚みは、ちょっとだけ薄くなっている気がしています。20代半ばまでは、ベクトルが自分に向いていましたし、自分の中だけでぐるぐると逡巡する機会が多かったなと。それで人を傷つけてしまったり、自分を傷つけたりすることもあったのですが、年々、自分のことを多少なりわかってきて、いい意味で、少しだけ諦めるタイミングもあったんですよね。そうすると、絶対に諦められないことが何なのかもわかってきたし、そういう頑ななところでさえ、年齢でまだ変化していて。それでも、今、29歳でまだ捨てられずに持っているものがあって、手放さずに後まで持っていられたものは、もしかしたら、自分にとってすごく大事なものかもしれない。私の性格をよくわかっている先輩からは、『とにかく、前より楽になっているのがわかるし、30歳以降はもっと楽しいはず』と言われているので、それを期待して、今持っているいろいろなものをそろそろ下ろしたいなとは思いつつ、下ろし方がわからないから持っておこう、という感覚ではまだありますね」
──今、木竜さんが挑戦している、もしくはしたいと思っていることがあれば聞かせてください。
「人から何かをしてほしいという感覚ではなく、してほしいことはまず自分でする。ということを、数年前からできる限りトライしているのですが、自分がしたことが返ってこなかったとしても、がっかりしないようにしたいですね。それは、人に期待しないということではなくて、期待はするけれど、潔さを持っておきたくて。まだどこかでがっかりしてしまう自分がいるので、たとえ返ってこなくても、それをそれとして受容して、次にいくまでの時間をもう少し短くしてけたら、相手にとっても自分にとっても風通しのいい関係になるんじゃないかなと」
演じる役柄のいちばん近くに行きたい
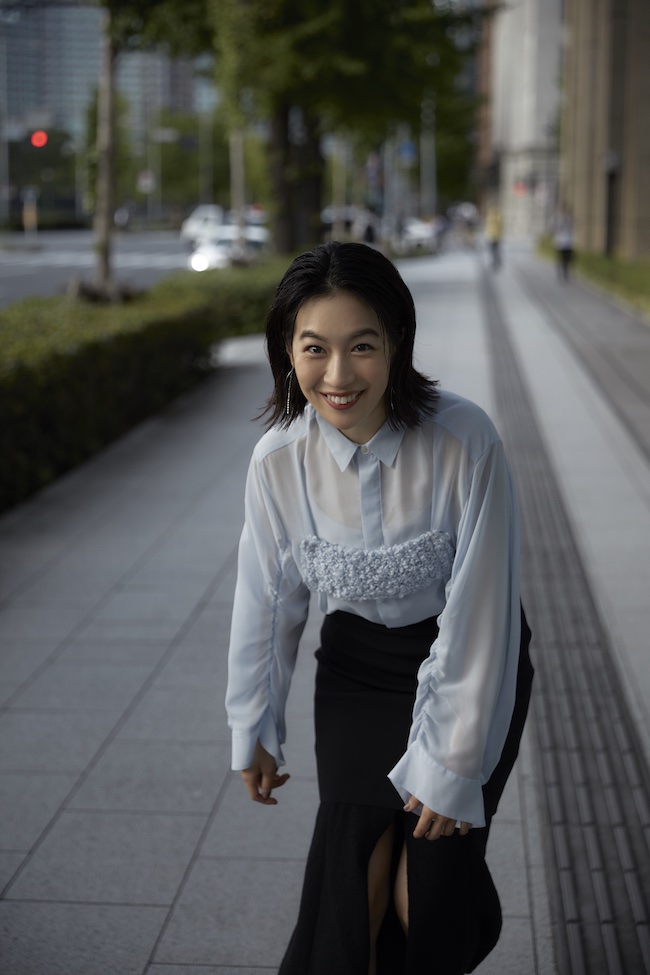
──木竜さんは、本当に丁寧に感情を言語化されますよね。お話上手というか。
「いやいや、私、話すことが下手という自覚があって、家族や周りの友人にも『何が言いたいかわからない』とよく言われていて。割愛するし、すぐ違う方向にいくし、言った瞬間に、『あ、違う、今のやっぱりなし!』と否定することも多いので(笑)。監督と話し合いをするときも、監督の頭に浮かぶはてなマークが見えて、申し訳なくなりますし、帰り道に、さっきの言い方じゃなくこう伝えたほうが言いたかった感覚に近かったと落ち込むこともよくあって。言葉にした後に、自分が思っていたものとは違うかたちになって出ていってしまうことが寂しくてたまらないんです。苦手意識があるからか、22歳くらいの頃からずっとやっているのは、本、ドラマ、映画の中で出合った好きな言葉や表現をノートに箇条書きで書くこと。それが活きているかはわからないですが、それをするようになってから、説明したいことからなるべく遠くない言葉を、前よりは見つけられるようになった気はします」
──得意じゃないという意識が最初にあるからこそ、雑じゃなく丁寧になるのかもしれないですね。完全にはわかり合えないとわかっているから、そこに近づけるというか。
「言葉を尽くすのも、相手とどこかで交われたらいいなと思うからですけど、私はまだたくさんの言葉を使わないとなかなか表現することが難しくて、もうちょっと量を少なくできたら、その分、相手側が使えるスペースが増えるんじゃないかと思うんですよね。そこはこれからの課題だなと」
──木竜さん、思いやりの塊じゃないですか。
「いや、こんなふうに言ってはいますけど、こうなりたいという夢を語っているみたいなところはあって。自分が器用じゃないのも、ちょうどいい塩梅ができないのもわかっているので、言葉にすることで『言ったんだから、ちゃんとやろう』と言い聞かせてるというか(笑)。こうしてインタビューを受けたり、人に伝えようというときには、なるべく抽象的になりすぎないように言語化できたらいいなと思う一方で、映画をつくるときは、個人的には、言い足りていないくらいの余白があるものが好きで。詩を読むみたいに、余白が多ければ多いほど、想像することを楽しめるので、『沈黙が最強!』という思いはあるのですが、作品の中では自分がすべきことを150%でやらなきゃいけない。だから、演じる役柄が自分とは全く違う人であるとわかったうえで、いちばん近くに行くということをしたいですし、そのためには、一人の時間をいい孤独として、ちゃんと面白がっていきたいなと思います!」
衣装/ブラウス¥37,400、スカート¥50,600/Harikae(ハリカエ 03-6300-5732)
『福田村事件』
1923年。千葉県福田村に暮らす澤田智一(井浦新)は、日本統治下の京城で日本軍による朝鮮人の虐殺を目撃していたが、妻の静子(田中麗奈)にも一切話すことはなかった。そんな中、9月1日に関東大地震が発生。流言飛語が飛び交う中、香川からやって来た薬の行商団の15人が朝鮮人と間違われ殺害されてしまう。福田村事件を題材に、社会派ドキュメンタリー作品を手がけてきた森達也が手がける初の劇映画。
監督/森達也
出演/井浦新、田中麗奈、永山瑛太、東出昌大、コムアイ、木竜麻生、松浦祐也、向里祐香、杉田雷麟、カトウシンスケ、ピエール瀧、水道橋博士、豊原功補、柄本明
テアトル新宿、ユーロスペースほか全国公開中
https://www.fukudamura1923.jp/
Photos:Takao Iwasawa Hair & Makeup:RYO Interview & Text:Tomoko Ogawa Edit:Sayaka Ito
Profile







