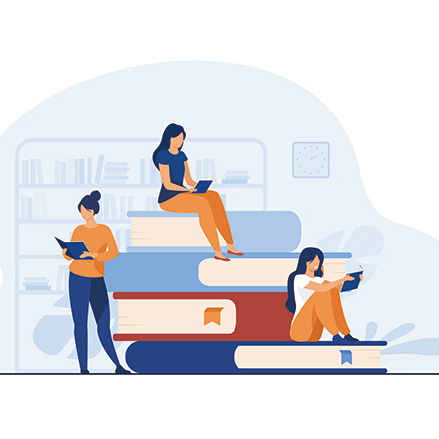西島秀俊インタビュー「主人公の喪失感は、僕たちみんなにつながっている」

本年(2021年)7月17日、日本を沸かせる朗報が届いた。第74回カンヌ国際映画祭で、村上春樹原作、濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』が、日本映画では史上初となる脚本賞(濱口と大江崇允の共同)を受賞したのだ。さらに国際批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞という3つの独立賞も獲得し、なんと計4冠の快挙。この破格の傑作の主演を務めたのは西島秀俊。世界が注目する気鋭・濱口監督との初タッグとなった本作の現場で、彼は何を感じたのか? なおインタビューは今年のカンヌ開催の直前、7月4日に行われたもの。西島さんの言葉の端々から浮かび上がる“快挙の予感”もキャッチできるはずだ。

密度と強度のある脚本をさらに掘り下げた
──179分のボリュームながら凄まじい緊張感が続く、素晴らしい映画でした。この『ドライブ・マイ・カー』に参加されたキャストの皆さんは、「とにかく脚本が面白かった」と開口一番に語っています。 「僕もまったくそうですね。圧倒されたのは“密度”です。こちらに手渡された一冊の脚本を読んだときに感じた出力のエネルギーが、通常の映画台本とはまったくレベルが違う。しかもその脚本が、映画の撮影期間中にどんどん変わっていくんですね。 俳優チームは本番以外の時間もずっとホン読みをしていて、それをまた濱口監督がフィードバックして、脚本が毎日ブラッシュアップされていく。それプラス、脚本とはまったく別に、例えば僕と妻・音(おと)役の霧島れいかさんの間で、この夫婦二人の間で前に起こったであろうことをホン読みしたりとか」 ──すごいですね。 「ただでさえ猛烈な密度と強度を備えた脚本なのに、それ以外の部分の掘り下げも尋常ではなかったですね。例えばいくつか質問を用意して、このキャラクターならどう答えるか? とか。しかも必ずしも正直に答える必要はないんですね。そのキャラクターなら(嘘をつく可能性を含めて)どう答えるか? ってことを各々が考えるんです。 そういった実際の会話での言葉の積み重ねも含めて、すさまじい量のテキストが現場でも行き交ったんですね。僕が演じた主人公の家福(かふく)という演出家の男は別に饒舌な人間ではないし、スクリーン上で発語しなかった言葉はいっぱいあるわけですけど、現場では膨大に生まれてくる言葉たちを常にカラダの中に入れている状態でした」
濱口竜介監督とのドリームタッグ
──なるほど。しかも村上春樹さんの同名短編小説(『女のいない男たち』文春文庫所収)を物語の土台にしつつ、チェーホフの『ワーニャ伯父さん』が多言語演劇として上演されるまでのリハーサルの時間がじっくり描かれます。映画の中では手話も含めた9つの言語が飛び交いますし、極めてハイコンテクストな構造ですよね。
「それだけに日本語でコミュニケーションするよりも“相手の話を聞く”ことが非常に重要でした。他者の声とテキストをとにかく注意深く聞く。大変な作業ですけど、それ自体がこの映画のテーマにつながっていると、みんな感じていたと思います。
やっぱりいま思い返すと、キツかったと言えばキツかったですね(笑)。でもやりがいは最高にありました。例えば、僕がこの映画の中で最もすさまじいなと思うのは、岡田将生君演じる若い舞台役者・高槻の独白のシーンなんですね。あそこは、岡田君という希有なほどピュアな心を持った役者さんの、本当の根っ子の特別な純粋さが出ている気がする。『なんか今、ものすごいことが起きてるな』っていう感動に打ち震えながら、あのシーンの現場に立ち会っていました。
しかもお芝居にまつわる細かい積み重ねのプロセスを、濱口監督がずっと一緒にやってくださいました。役作りといっても、僕ら役者が自分ひとりで役について想像して、自分のやり方だけでやっていたら、到底ここまではいけない。登場人物の本質や隠された多層性までは全然つかみきれてなかったように思います」
──濱口竜介監督と西島さんのドリームタッグは「ついに来たか」という想いがありまして、個人的にも非常に待ち望んでおりました。西島さんも村上春樹作品を濱口監督が映画化すると聞いて興奮したと公式コメントで語られております。濱口監督の映画はずっとご覧になっていた?
「そうですね。濱口さんが東京藝術大学の大学院修了制作として撮られた『PASSION』(2008年)は東京フィルメックスのコンペティション部門で初めて観て、大変な衝撃を受けました(西島さんは2017年まで東京フィルメックスの実行委員会の理事を務めていた)。もちろん『寝ても覚めても』(2018年)なども非常に面白く観ましたし、『すごい監督が日本から登場した』という驚きとうれしさを率直に感じていました」

──世代的には西島さんのほうが少し上になります。
「濱口監督は1978年生まれとのことなので、僕のほうが7歳ほど年上ですね。ただ初めて濱口さんとお会いした時に、『カサヴェテス2000』っていう特集上映の話になったんですよ。当時、その企画でジョン・カサヴェテス監督の初期の傑作である『ハズバンズ』(1970年)『ミニー&モスコウィッツ』(1971年)『愛の奇跡』(1963年)が日本公開されたんです。
僕はそのときに、人生が変わるくらいの衝撃を受けたんですね。そうしたら濱口監督もやっぱり決定的な衝撃を受けたと言っていて」
──濱口監督は大学の卒論がジョン・カサヴェテス論ですものね。
「そうですね。だから僕の中では“かつて同じ場所に居た人たち”といいますか、同じ映画館で衝撃を受けた人たちが、またここに集まって、映画を一緒に作ることができている。すごく運命的なものを感じます。20年前のカサヴェテス特集もそうですけど、濱口監督ともたぶん知らないうちに映画館の中で何度もすれ違っていたんだろうなって」

日本に住む私たちの経験したことが海外へ伝わる作品
──カサヴェテスというと、西島さんがご出演された『風の電話』(2020年/第70回ベルリン国際映画祭国際審査員特別賞を受賞)の諏訪敦彦監督もすごく影響を受けられた一人ですよね。西島さんとは初期の『2/デュオ』(1997年)で組んだ監督でもある。
「そういえば諏訪監督、今回広島でロケしている時、いきなり現われたんですよ(笑)」
──なんと(笑)。
「たまたまその時、広島で映画祭があって(広島国際映画祭、2020年11月21日~23日開催)、そこで講演しに来たとは聞いていて(『風の電話』メイキング上映に合わせたティーチイン)。でも撮影で会えないかなと思っていたら、いきなり現場に現われて(笑)。『どうしたんですか?』みたいな」
──思えば『風の電話』と『ドライブ・マイ・カー』には連続性や共通性がありませんか?
「本当にたまたまですけど、ありますよね。車で移動することだったり、いまの日本のリアルな土地や人々の風景が映っていることだったり。あるいは自分が演じた人物像もそうですね。『風の電話』で僕が演じた森尾というキャラクターは、福島県出身で、震災で家族を失ったという過去を持つ男性でした。
『ドライブ・マイ・カー』で僕が演じた家福も“ある出来事”の前と後で、なにか人生が断絶してしまった男の役なので。彼が抱える喪失感は、おそらく僕たちみんなが、日本社会が経験したことにつながっていて、特に海外の方々から見ると、“いまの日本”が抱える心性みたいなものを感じ取ってもらえるんじゃないかと思っています」

車の中という特別な空間で起こりうること
──原作では黄色い車なのですが、映画の中で西島さんが乗車される赤い「サーブ900」も印象的です。
「現在では生産が終わっている車種なのですが、今回は劇用車の担当の方がプライベートで大切に乗られている車をお借りしたと聞いています。
この映画では車の中のシーンがとても多いんですが、本当に独特の不思議な空間だなとあらためて思いました。相手としゃべりながら、向き合わないですよね。運転席や後部座席に座っている人間が、視線を交わさずに同じ方向を向いてしゃべっている。時には外を向いて話していたりとか。逆に黙っている時間も同じ空間にいるわけで、しかもイヤじゃない。自分がしゃべらないときは相手の声に集中していたり」
──「移動する密室」ですもんね。
「はい。やっぱり特殊な空間だと思います。車の中って“もう一つの自分の場所”っていう感覚もありますし。僕は実際、本当に独り言のようにブツブツと台詞を言ったりもしていますし。逆に大きい声を出しても大丈夫ですよね」
──車という個的空間に、専属ドライバーのみさき(三浦透子)という「他者」を招き入れて、ハンドルを任せるってすごくシンボリックな設定ですよね。
「面白いのは『ドライブ・マイ・カー』って言ってるけども、実は家福はほとんど自分で運転していないんですね(笑)。前半は霧島れいかさん扮する妻が運転していることが多いし、後半は“運転できなくなった男”の話でもあるので。
いつも誰かに運転してもらっている男の映画……考えれば、これも奇妙な話ですよね。ドライバーが運転しながら話すことって、よくある場面だと思うんですよ。運転中って意識と無意識が自動的に混在している状態だから、“適当に話す”ことが向いている。でもこの映画では、運転してもらっている側の人間が話すという。“普通ではない”ですよね、ちょっと」
──あの車の中こそ、村上春樹と濱口竜介が混じり合う場所のような気もします。
「確かに。濱口監督はこれまでの映画でも、恋人同士だったり、関係としては近しい相手の得体の知れない部分やどうしても判らない部分を注視し、人と人がどんどん断絶していく様を描いてこられたと思うんですけど、そこは村上春樹さんの原作ともつながりますよね。でも、この映画には濱口さんならではのところがいっぱいある。原作からまったく外れているわけではないけれど、でも最終的には濱口監督独自のものになっている。
もしかすると濱口監督が目指したのは“原作の、その先”なのかもしれない。断絶や喪失だけで終わらず、その先の希望や融和の可能性をつかめることができるのか? という模索を、作品を通して試みているのかなというふうに感じます」
『ドライブ・マイ・カー』
舞台俳優であり演出家の家福(かふく/西島秀俊)は、愛する妻の音(おと/霧島れいか)と満ち足りた日々を送っていた。しかし、音は秘密を残して突然この世からいなくなってしまう──。2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過去をもつ寡黙な専属ドライバーのみさき(三浦透子)と出会う。さらに、かつて音から紹介された俳優・高槻(岡田将生)の姿をオーディションで見つけるが……。
監督/濱口竜介
出演/西島秀俊、三浦透子、霧島れいか/岡田将生
原作/村上春樹
dmc.bitters.co.jp
Photos:Kouki Hayashi Styling:Takafumi Kawasaki Hair & Makeup:Masa Kameda Interview & Text:Naoto Mori Edit:Sayaka Ito
Profile