Numero TOKYOおすすめの2022年10月の本

あまたある新刊本の中からヌメロ・トウキョウがとっておきをご紹介。今月は、奇しくもきっかけを同じくして生まれたといわれるモンスターの元祖「ヴァンパイア」と「フランケンシュタイン」を題材とした国内外の新作小説。そしてイギリスから長編ミステリの傑作をお届け。

『あの子とQ』
著者/万城目学
価格/¥1,760(税込)
発行/新潮社
ミステリとしても楽しめる、高校生吸血鬼の冒険物語
古今東西、吸血鬼を題材とした作品は多々あるが、一風変わった“吸血鬼もの”が新たに誕生した。それが万城目学による本作『あの子とQ』だ。何が変わっているかといえば、主人公である嵐野弓子をはじめとする一族は正真正銘のヴァンパイアでありながらも人間の血を吸わず、現代社会に溶け込みながら人間と同じように暮らせる種として変化をとげている点だ。
そんなニュータイプともいえるヴァンパイアであり、高校生でもある弓子が17歳の誕生日を10日後に控えた朝に絶叫しながら目覚めるところから物語は始まる。何せ自室の天井に「直径六十センチほどの、ウニのように長いトゲトゲに全体を覆われた得体の知れぬ物体」が浮かんでいたのだ。あわてふためく弓子をよそに「おお、あと十日か。いよいよ、十七歳か」と呑気に会話を繰り広げるパパとママいわく、Qと名乗るその存在は17歳を迎えると同時に行う、潜在的な血への興味を失う「脱・吸血鬼化」の儀式に参加するための条件を弓子が満たしているかどうかを確認するためにつかわされた証人だという。
吸血鬼であれば誰もが通る道とはいえ、10日間も不気味な存在に四六時中監視され続けるなんて耐えられない!と憤る弓子。しかし、ある出来事をきっかけに大きな謎を残したままQは忽然と姿を消してしまう。謎を解明すべく、弓子は調査に乗り出すが……。
現代を生きる高校生吸血鬼の青春物語のように始まりながら、くだんの“出来事”以降は謎を探るミステリのような展開となる本作。万城目作品ならではのコミカルさもたっぷりで、一瞬たりとも退屈せずに一気読みしてしまう人も多いはずだ。また、ミステリ要素が強いだけでなく、なぜ同じ社会に属する人々の中でも対立が生じてしまうのかなど、対立の根っこにあるものについても考えさせられる内容にもなっている。ジュブナイル冒険譚として読んでも良し、ミステリとして読んでも良し。文句なしの面白さをたっぷりと味わってみて。
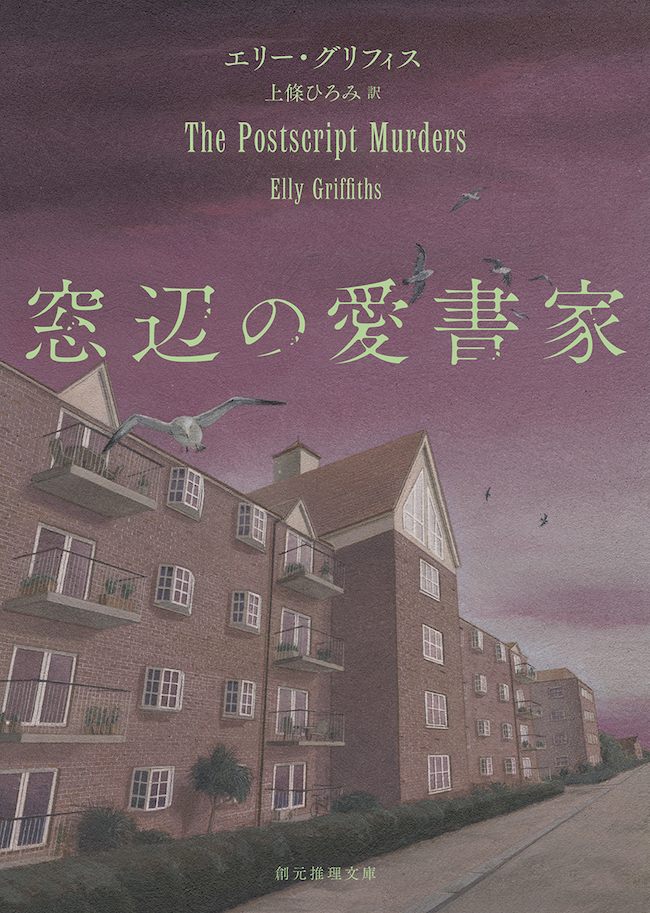
『窓辺の愛書家』
著者/エリー・グリフィス
訳/上條ひろみ
価格/¥1,210
発行/創元推理文庫
読書の楽しみを再発見できる傑作ビブリオ・ミステリ
2020年のアメリカ探偵作家クラブのエドガー賞最優秀長編賞を受賞した『見知らぬ人』の続編となる、イギリスのベテラン作家エリー・グリフィスによる長編ミステリ。英国推理作家協会最優秀長編賞(ゴールド・ダガー賞)の2021年度最終候補作にも選ばれた本作は、読み応えもミステリ作品としての完成度も前作からさらに高まっており、読む人によってはオール・タイム・フェイバリットな一冊となりそうだ。
物語は、“殺人コンサルタント”と名乗り、多くの作家の執筆に協力していたミステリ愛好家の老婦人ペギーの死から始まる。心臓発作が死因とされながらも不審に思った介護士のナタルカは、ウェスト・サセックス警察犯罪捜査課のハービンダー刑事に相談しつつ、ペギーが暮らしていた高齢者用住宅〈シービュー・コート〉の住人であるエドウィンと、〈シービュー・コート〉の向かいにあるカフェのオーナーであり元修道士のベネディクトと真相を探りはじめる。しかし、ほどなくナタルカとベネディクトがペギーの部屋を調べていたところ、銃を持った覆面の人物が侵入し、一冊の推理小説を奪って消える。さらに自作の献辞でペギーの名前を挙げていた犯罪小説家が遺体で発見され……。
ハービンダーが捜査を進める中、ナタルカとエドウィンとベネディクトの3人は、一連の出来事の裏にどのようなつながりがあるのかを別の筋から探っていく。と同時に、ロシアの脅威が高まる前にウクライナから渡英していたナタルカを追う正体不明の人物の存在が、さらなる謎と緊張感を生み出していく。次から次へと起きる出来事に張られた伏線が見事に回収されるラストには、読んでいて思わず感嘆してしまうはずだ。
また前作から引き続き登場し、自身について“ウェスト・サセックスで最も優秀な、同性愛者でシーク(教徒)の刑事”と心の内で皮肉を言うハービンダーにも、ぜひ注目してほしい。同居する両親にカミングアウトできず、私生活ではどこか鬱々としている彼女に一筋の光明が差し込む展開も、心地良い読後感をもたらしてくれる。
前作『見知らぬ人』を未読でも十分に楽しめる内容となっているので、まずは本作を読み、もしハービンダーのキャラクターに惹かれたら、前作もそろえることをおすすめしたい。特に本作は完成度の高いビブリオ・ミステリであると同時に、読書の楽しみを再発見できる作品でもあるので、秋の夜長のお供にぜひ。

『フランキスシュタイン ある愛の物語』
著者/ジャネット・ウィンターソン
訳/木原善彦
価格/¥4,180
発行/河出書房新社
あらゆる境界を超越した先に見えてくる世界の姿
長編『灯台守の話』、半自伝的小説である『オレンジだけが果物じゃない』などの作品で知られるジャネット・ウィンターソンによる待望の最新作。題名からも分かるようにメアリー・シェリーによる不朽の名作『フランケンシュタイン』を題材としているのだが、ひねりの効いたユーモアに定評のあるウィンターソンの作品だけあり、単なるオマージュ以上のものとなっている。
物語は1816年に、メアリー・シェリーが『フランケンシュタイン』を(そしてジョン・ポリドリが吸血鬼小説の元祖となる『吸血鬼』を)創作することになるディオダディ荘の怪奇談義の場面から始まる。しかし、ほどなくして、医師のライ・シェリーがセックスドール販売者に取材するためにテネシー州メンフィスで開催されているロボット工学関連の展示会を訪れる場面へと変わる。
ふたつの時代が交錯しながら物語は展開していくのだが、生と死、肉体と精神、女と男、現実と虚構など、さまざまな境界が登場人物たちによって超越されていき、時空を超えた壮大なスペキュレイティブ・フィクションとしての姿を現していく。
サブタイトルに「ある愛の物語」とあるように、ラブストーリーとして読む/解釈することができるのだが、それ以外の読み方/解釈もしっかりできる内容となっているのが、この作品の最大の魅力だろう。永遠に変わらないと思い込んでいた境界が崩れ、思うがままに超越できるようになったときに見えてくる世界の新しい姿を、どうか思い思いに楽しんでほしい。
Text & Photo:Miki Hayashi Edit:Sayaka Ito






