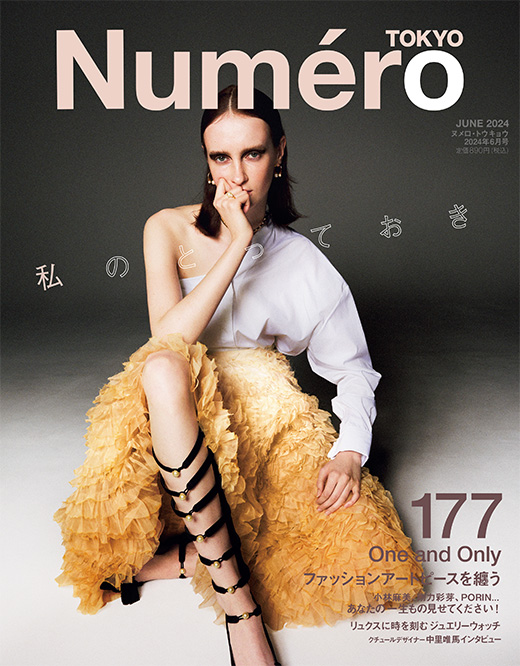森山大道という伝説
2006年、小誌創刊準備号(0号)東京特集に写真を提供してくれた写真家の森山大道。今回の写真特集にあたり、東京の写真を再度お願いした。これまでもこれからもカメラを手にして東京を彷徨う森山が、現役にして伝説となった理由をひも解く。(『Numéro TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2021年1・2月合併号)
 新型コロナウイルス対策への配慮から延期されていた映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』(以下『過去は〜』)が来年4月、ついに公開される。この日本を代表する写真家を取材したドキュメンタリー映画の公開は『≒森山大道』からおよそ20年ぶり、『森山大道「サンパウロ、路上にて」』から12年ぶりとなるが、この間、国内外で続いてきた“森山大道フィーバー”はますます加熱しているように思える。2019年には写真界のノーベル賞と称されるハッセルブラッド国際写真賞を受賞した森山は、すでに80歳を超えているが、ファンに老若男女の偏りはなく、最近では若手コレクターが金沢市にオープンさせた美術館KAMU kanazawaで、代表的なモチーフである唇を写した写真のインスタレーション「Lip Bar」が日本初公開されるというニュースも飛び込んできた。
新型コロナウイルス対策への配慮から延期されていた映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』(以下『過去は〜』)が来年4月、ついに公開される。この日本を代表する写真家を取材したドキュメンタリー映画の公開は『≒森山大道』からおよそ20年ぶり、『森山大道「サンパウロ、路上にて」』から12年ぶりとなるが、この間、国内外で続いてきた“森山大道フィーバー”はますます加熱しているように思える。2019年には写真界のノーベル賞と称されるハッセルブラッド国際写真賞を受賞した森山は、すでに80歳を超えているが、ファンに老若男女の偏りはなく、最近では若手コレクターが金沢市にオープンさせた美術館KAMU kanazawaで、代表的なモチーフである唇を写した写真のインスタレーション「Lip Bar」が日本初公開されるというニュースも飛び込んできた。
写真を解体した、その先へ
『過去は〜』は世界最大の国際写真フェア「パリ・フォト2018」のシーンから始まる。この場で初披露され即完売となったのは、デビュー作『にっぽん劇場写真帖』(1968)の“復活”版。映画はこの本の制作から発表までを追いかけながら“孤高のレジェンド”森山大道の実像に迫る試みだ。
デビュー作の時代から50年間以上、森山の基本的な撮影手法であり続けてきたのが、街を徘徊しながら撮影するスナップショット。本作では彼の撮影に密着する貴重なシーンがたびたび登場するが、そこにインサートされた25年前のテレビ映像で森山は、こんなふうに語っている。「学校をさぼってウロウロ歩くのが好きだったんですね。映画の看板を見たりスチールを見たりショーウィンドウを見たり……今の僕も一緒なんですよ……写真を撮っていて、ヒリヒリ、ヒリヒリするような、そういうものをいつも感覚しますよね」
被写体を仕留めるかのように素早く撮られた森山の写真は、しばしば焦点がボケ、画面はブレる。さらに粒子を粗く、ハイコントラストで焼き付けたイメージは “アレ・ブレ・ボケ”と称され、森山作品を語る上で欠かせない形容詞ともなってきた。この、世界の表層をかすめ取るかのような独自の表現に行き着くまでの道のり──他界した盟友・中平卓馬との出会い、伝説となった写真同人誌『プロヴォーク』への参加、そして写真集『写真よさようなら』(1972)の制作等々──について語る森山自身の言葉たちは、この映画の最も大きな見どころと言っていいだろう。いわく、「写真をある意味で解体してみたいと……生意気にも思って。最終的に解体されたのはこっちなんだけど(笑)……写真は強靭だから、簡単に解体できるわけがない」といったように。そして経験する、スランプと復活。『写真よさようなら』で写真の解体を試みた結果、人生もままならないほどのスランプに陥り、そして自らの答えを持って帰還した。そんな彼の生きざまこそ、現役でありながら伝説の写真家と呼ばれるにふさわしいと、この映画で再確認した。

そしておそらく、この写真家と作品の抗いがたい魅力に引きつけられ、自身の道を追求する者たちもまた、森山を伝説たらしめている存在といえるのではないか。『過去は〜』では、編集者・神林豊と造本家・町口覚をはじめとした、それぞれの仕事ですでに名を知られた者たちが、写真集復活のプロジェクトに打ち込んでいるが、森山に出来上がった本を初めて見せるときの少年のような表情が印象的だった。彼らのみならず、写真家や編集者、デザイナーの道に進んだ者、出版社を立ち上げ、もしくはギャラリーを設立した人など、森山から決定的な影響を受けて人生を決断した者たちは数えきれないだろう。それほどまでに強く、深く人生に影響を及ぼす写真など、めったにない。彼らを魅了する、森山作品の力の震源はいったい何なのか?
アノニマスな世界の複製
今回のパンデミックで多くの展覧会が中止となるなか、映画『過去は〜』と連動するかたちで企画された個展「森山大道の東京 ongoing」(東京都写真美術館6月2日〜9月22日)が開催されたことは幸いだったが、図録写真集に収められた文筆家・大竹昭子のテキスト「路上の一歩スナップショットを駆動させるもの」に、見逃せない事実が紹介されていた。森山の自室のベッドサイドには2点の複製写真が掛けられているという。一点は、190年前にニセフォール・ニエプスが8時間かけて撮影した世界最古の写真。もう一点は、その原版を訪ね森山自ら撮影した写真だ。この光と影という写真メディアの原点を示すイメージこそ、森山がスランプから復活するきっかけを与えてくれたという。
写真の本質は、光と影にある。この発見が、彼がたびたび発言してきた「写真は複写(コピー)である」、そして「写真は存在そのものがアノニマスなもの」という信条につながっているといえるだろう。ここで思い出すのが、映画『≒森山大道』での発言だ。自分の意識や観念を完全に排除してシャッターを切ることは不可能だが、その矛盾を抱えながらも、撮るべきイメージを追いかけて世界を決めつけることはしたくない。いわく、世界は「もっとバラバラにその辺にあるんだよ……さまざまにあるその断片を、きりもなくコピーして複写して……それで写真とは何だろうって、そこからもう一度問いかけていかないと」
世界の断片のアノニマスな複製として撮影された森山の写真が放つヒリヒリとした感覚は、もしかしたら既成の価値観や自らの思考すらも乗り越えるような自由、もしくは未来の予兆というべきものなのではないだろうか。映画のタイトルとなった“過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい”というフレーズは、森山がふと目にした読み人知らずの言葉。写真家が未来を懐かしく感じるのは「来るべき未知の時間や風景が、街角の隅のそこここに予兆となって浮遊しているのを日ごろ実感しているから」だという。現在(いま)なくしては、過去も未来もない。後戻りできないほどの変革が余儀なくされる現代だからこそ、森山の作品はより心に迫ってくるように感じる。まるで、おまえは自由なんだよ、自分の人生を生きろよと語りかけてくるかのように。
Photos:Daido Moriyama Text:Akiko Tomita