少女の毒を味わうための小説6選
“少女”たちが持っている特有の毒を描いた、読むものの心にこびりつく、“少女”をモチーフにした小説を厳選ピックアップ。(「ヌメロ・トウキョウ」2018年6月号より)
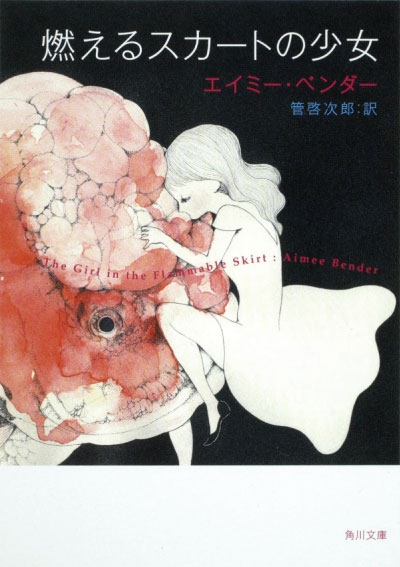
『燃えるスカートの少女』エイミー・ベンダー
¥600(角川文庫) スカートが燃え上がったのを感じた最初の一瞬、あの子は何を思ったのだろう? 蝋燭のせいだとわかるまえに、彼女は彼女自身に火がついたのだと思わなかっただろうか 父がくれたのは、石でできたバックパック。かつがなくてはならないきまりと言われ、それを背負って少女は学校へ行く。先生に重いと訴えると、先生はティッシュペーパーを一枚渡し、軽いものをみせてあげたかっただけと言う。車椅子の父といるときに、もし火事になったらと想像する。足りない何か埋めようとするように邪で美しい思想が浮いては消え、寂しさだけが残る。夢の中の出来事のようなのに刺さってとれない、16の短編集。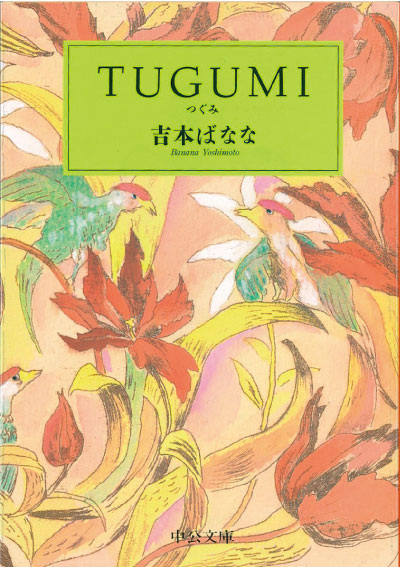
『TUGUMIつぐみ』吉本ばなな
¥457(中公文庫)
あたしは平気でポチを殺して食えるような奴になりたい。もちろん、あとでそっと泣いたり、みんなのためにありがとう、ごめんねと墓を作ってやったり、骨のひとかけらをペンダントにしてずっと持ってたり、そんな半端な奴のことじゃなくて、できることなら後悔も、良心の呵責もなく、本当に平然として『ポチはうまかった』と言って笑えるような奴になりたい。
海辺の田舎町を離れて東京で暮らすことになったまりあが、従姉妹のつぐみと姉の陽子、そして不思議な青年・恭一と故郷で過ごす、最後のひと夏の記憶の物語だ。幼い頃医者から短命宣言をされたことから、ちやほやと甘やかされまくったつぐみは、とびきりの美少女だが、意地も口もとびきり悪い。つぐみが本当に怒りを表すときに見せる残酷さは、死と隣り合わせに生きることで磨き抜かれた心が信じる正しさで、だからこそ眩しく映る。

『少女七竈と七人の可愛そうな大人』桜庭一樹
¥600(角川文庫)
おとなの男たちからじろじろと眺めまわされるたびにわたしは怒りをかんじる。母に。世界に。男たちなど滅びてしまえ。吹け、滅びの風。
不義の子として「たいへん遺憾ながら、美しく生まれてしまった」川村七竈。成長と共に顕著になる母になかった「禍々しき異形の証」である美貌は、男たちの落ち着きを失わせ、出自にまつわる屈辱を七竈にもたらすものでしかない。鉄道模型と幼馴染の少年だけを友とし、孤高の青春を送る少女の閉ざされた世界を、不幸な大人たちが現れては乱していく。母の呪縛を解くために決断を下す少女の成長を描く、哀切とやさしさに満ちた物語。

『水の輪』江國香織(『すいかの匂い』収録)
¥460(新潮文庫)
私たちは、庭に置かれたそのまるいビニールプールの中で、見られていることを全身で知っていた。
見栄から重ねてしまった小さな嘘、親の庇護下にいる優越感が引き起こした出来事など、人の少女のほろ苦い夏の記憶を描いた短編集。過去形で語られる物語は、過去に犯した過ちへの懺悔話としても読める。だが、どの過ちも誰にとって身に覚えがありそうなもののため、読み手は自分の思い出を重ねずにはいられなくなる。蠱惑的だった少女性も、大人になるにつれて単なる共感要素へと成り下がるという現実の苦味も感じさせる一冊

『マリーの愛の証明』川上未映子
(『ウィステリアと三人の女たち』収録)
¥1,400(新潮社)
でも、それが溢れてしまったときに、きっと自分は死んでしまうのだとマリーはかたく信じていた。どんなふうに死ぬのかはわからない。事故なのか、殺されるのか、自分で死ぬのかは、わからない。
寮に暮らす少女たちが、愛と存在について言葉を交わすピクニックでのひとときを描いた本作。恋人だったカレンに、彼女のことを本当に愛していたかと尋ねられるマリー。不確かな思考を言語化することを諦めず、懸命に言葉をつなぐマリーに対してカレンが見せる態度は、移り気な少女の残酷さを感じさせる。「自分にしかわからない話をしながら、それでも誰かとわかりあえることを夢み」る少女の儚さを、愛おしく感じる思索的な短編。

『女生徒』太宰治
¥440(角川文庫)
ああ、こんな心の汚い私をモデルにしたりなんかして、先生の画は、きっと落選だ。美しいはずがないもの。いけないことだけれど、伊藤先生がばかに見えてしようがない。先生は、私の下着に、薔薇の花の刺繍のあることさえ、知らない。
『斜陽』など女性独白体作品を得意とした太宰治。女性読者から送られてきた日記を題材とした本作では、一日を通してうつろう少女の意識の流れが描かれる。自分が醜いと思う大人に対して容赦なく嫌悪を表わす少女だが「、だんだん俗っぽくなるのね」という指摘に怯え「少女のままで死にたくなる」など厭世的な独白を繰り返す。いつの時代も少女は、若さゆえの傲慢さから毒を吐き、その毒に自らも侵食されて苦しみ悩む存在だ。
Text:Miki Hayashi, Tomoko Ogawa Edit:Sayaka Ito






