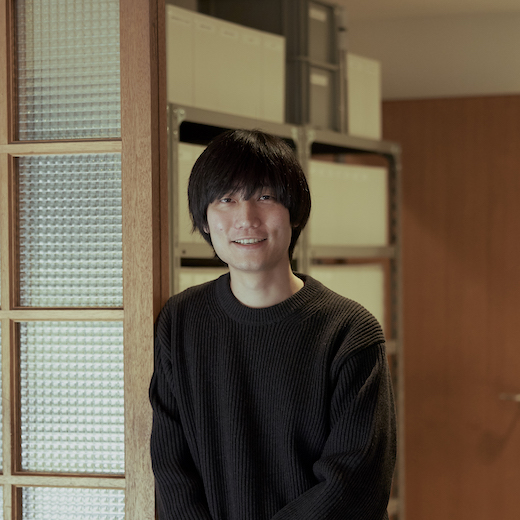奥山由之インタビュー「個から個への強い気持ちは人間の“普遍”にタッチできる」
写真家・映像監督の奥山由之がデビュー以来12年間に渡って手掛けてきたクライアントワークをまとめた写真集『BEST BEFORE』を刊行。米津玄師、星野源、あいみょんらアーティストとのコラボレーション、ポカリスエットなどの広告写真、大河ドラマ「麒麟がくる」のメインビジュアルなどなど、500ページ超の大ボリュームに仕上がった1冊は、とてもエネルギッシュで混沌として、無邪気で、ユニーク。個人の作品制作や映像の監督業と並行して、コマーシャルの領域でも唯一無二の表現に挑戦し続けてきた奥山が語る、創作への思いとは。

ジャンルや年代を越えてクライアントワークを編纂した写真集『BEST BEFORE』
──これまで17冊の写真集を作ってきて、今回クライアントワークをまとめて写真集を作ることになったきっかけを教えてください。
「2年前に活動が10年の節目を迎えて、そのタイミングで、クライアントワークだけをまとめてみようと思ったのが最初のきっかけでした。点で散乱していた写真が、物理的に編集不可能な“本”という状態にまとまると、数十年後、自分が今の自分ではなくなった時に、客観的に、その作品が持っている個性や本質に気付けるのではないか、という思いからスタートしました。なので本作りは、ある種のタイムカプセル的な感覚がいつもあります。当初は『PORTFOLIO』というタイトルで進めていたのですが、内容を編み上げる過程で『BEST BEFORE』(=賞味期限)という今のタイトルに落ち着きました」

──もともとは違うかたちで進んでいたんですね。
「最初の予定ではもっとページ数が少なくて、逆に判型は大きかったですね。経緯はあれど、クライアントワークをまとめるのは、一緒に写真を作ってきて下さった方々に掲載許可をいただくという意味でも信頼関係がないと実現できないので、無事に完成できたのは本当に皆さんのおかげです」
──被写体やスタッフはもちろん、案件ごとにご一緒する方が違えば仕上がりも違いますよね。
「そうなんです。僕は企画ごとに全然違う撮り方をしてきました。写真における自分の個性が何なのか、表面上の統一感がないので、明確な言語化が難しいほうだと思います。よくフィルムでしか撮らないと勘違いされるのですが、デジタルでしか出来ない撮影手法をあえて活かして撮った写真も中にはあります。
頼んでくださったアーティストやクライアント、アートディレクターに対して、まっすぐに向き合うと毎回同じ撮り方ではベストが尽くせない。だからその都度手法を変えていくわけですが、そうすると結果として混沌とした内容の1冊になりました」

「個から個への強い気持ちは人間の“普遍”にタッチできる」
──普段の仕事では、一緒に創作をしてくれている身近な人に向けて作るということを以前取材でお話していましたが、今回のようにクライアントワークをまとめた写真集は、具体的な読者を想定しながら作ったのでしょうか。
「そこは個々のお仕事の考え方と変わりありません。まずは一緒に作り上げてくださった方々が、奥山と創作をして良かったなと思えるもの作りをしたいです。その上で、少人数から対少人数に対して届ける強い気持ちがこもっていないと、結果的に大多数には伝わらないと思う。個から個への太くて短いベクトルが何よりも強い。湖に大きな石を投げ込むと、フワーっと波紋が周囲に広がっていきますよね、あんなイメージです。『大衆に向けて』なんていう作り方をしても、想定している受け取り手ひとりひとりは、“大衆”ではなく“個人”ですから。ただ大人数の目を撫でるだけで、記憶に残らないような脆弱な作りに終始してしまう。それは避けたいので、何を作るにしても、誰か1人や少人数の誰かへの気持ちを具体的に思い描いて作っています」
──たしかに、最終的な受け取り手も結果として個人ですよね。
「だから個から個への強い気持ちは、結果的に人間の普遍的な感情や情景にタッチできると思っていて。今回も一緒に本をつくって下さったアートディレクターの平林奈緒美さんや編集者の新庄さん、寄稿文を執筆してくださった伊藤さんや河尻さん、推薦コメントを書いてくださった米津さんに届けたいという思いがまず最初にあります。同時に読者への意識として、これから写真を撮りたいとか、写真を仕事にしたいと思ってる自分よりもキャリアや世代が若い人たちに見てもらいたいという気持ちもあります」

──20代以下のこれからの人たちですね。
「巻末のクレジットページには、撮影に関わってくださった方々のお名前が掲載されています。ものを作るというのは一人ではできない。自分自身と向き合うというのは創作における当たり前の行為でありながら、さらに『他者とのコミュニケーションを重ねないことには、本当の意味で人の心に深く届くものは作れない』という事実が、創作を始める人の前提認識としてまずあってほしいんです。僕の個性として認識されているものは、決して僕だけの力ではなくて、打ち合わせの会話やメールから始まって、誰かと影響を与え合った結果として、それがたまたま写真や映像という媒体になっていたということなんです。ものづくりの過程で他者とコミュニケーションを交わすことの大切さをこの本を通して実感してもらえたら嬉しいです。他者というのは、必ずしも人間だけではなくて、環境や社会なども含めた自分以外のすべてです」
──そもそも写真集『Girl』でデビューして以降、コマーシャルの領域でも写真を撮りたいと思ったきっかけは何だったんですか?
「コマーシャルでも写真を撮り始めた十数年前、街で見かける写真、例えば駅で目にするポスターは、2秒で言語化できるような、情報データそのものみたいな写真が多いと思っていました。言語的すぎて余白がないといいますか、言語をただ写真に置き換えているみたいな、それ以上でも以下でもないというか、つまり写真である必然性があまりないような気がしていました。情報データとしては瞬時に理解できるけれど、受け取り手それぞれの個性で感じたり考えられる余白がないので、すぐに別の新しい情報に上書きされてしまう。言いたいことは分かるけど、記憶や感情に残りづらい」

──プレゼンの時に全部理屈で説明できちゃうような。
「人に伝えるってそういうことじゃなくて、『この気持ちは何だろう』とか、『これってどういうことなんだろう』と受け取り手が感情を重ねて考えてしまうような、その個々人の情景にタッチするという行為なんだと思うんです。見る人が想像したり考えることも含めて創作していくことができないと写真である意味もあまりない。写真は瞬間芸術であるがゆえに、こうとも取れる、ああとも取れるみたいな、曖昧さゆえの表現の余白や揺らぎ、が魅力であるはずなのに、微塵の余白も作らず、絵コンテの段階でガチガチに固められたこれ以上でも以下でもないみたいな、言葉よりも言葉らしい写真が多く思えたんです。写真というよりは情報画像に近いかもしれません。
こんな言い方は適切じゃないかもしれませんが、極端に言うと、時代が進むにつれて観る側の感性を信じていない表現が多くなってきている気がします。『分かりやすくないとどうせ伝わらないだろう』みたいな諦めのため息混じりで作られたようなものが。それは観る人に対して失礼な姿勢だと思っています。少し話が逸れてしまいましたが、僕はそういったものではなく、ちゃんと個々人の感情に触れられるものを作りたくて、続けてきました。なので、作ったものが誰かの心に伝わり、自分もこういった表現をしたいなと思う人がもしいたら、とても嬉しいです」

「僕らしいと思われているものも、僕だけが考えて作り出したものじゃない」
──コミュニケーションの大切さや、チームワークとしてのクリエイティブの大事さをおっしゃっていましたが、奥山さんの創作は、個人の強い作家性で作り上げていると思っている方々も多いのではないでしょうか?
「当たり前のことですが、奥山くんらしいよねと思われている創作があったとしても、それは僕だけの力で作られているわけではありません。僕自身の発想や考え方、アイデアに対して誰かが意見を述べてくれて、それを受けて僕もよく考えてまた意見を相手に伝える。そのコミュニケーションの過程にきっと自分らしい個性があるのであって、発想そのものやアイデアは、きっと世界中探せば同じようなことを考えている人は他にもいるはずです。だから仮にどんな個性的な作家性であったとしても、それは一人では作り上げられないものだと思っています」
──なるほど。関わる人の意見や世界が全部合わさった結果ということですね。
「決して頭の中にある発想が天才的なわけではなく、もし僕に個性が認められているとしたら、人とどうコミュニケーションを取るかというところにあるだけだと思います。クリエイターやアーティストと呼ばれる人たちは、唯我独尊の精神で、自分の中で爆発する世界を表現するみたいなイメージがありますけど、例えそういう描き方をされている作家であったとしても、その人なりの世界との接し方にちゃんと個性があるはずなんです。一人だけの人間の内面から湧き出てくるものはそんなに膨大にはなくて、やっぱり誰かと影響し合う、考えや思想を反射し合ってこそ個性的なものを生み出していくのが人間だと思っています。
先日対談した小説家の朝吹真理子さんは『浸食』という言い方で、小説を書く行為自体はひとりだけれど、登場人物がどういう人なのかその人の中に入って対話、浸食し合うみたいな感覚があると説明されていました。コミュニケーションの相手は必ずしも外側に存在していなくてもよくて、頭の中にある世界もひとつの他者。何かしらと向き合い、正直で深いコミュニケーションとることで、自分らしいクリエイティブに到達できるのではないか、と思っています。この12年間でそのことを勉強できて、とてもありがたかったです。関わってきて下さった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」
──一緒に作ってきた人たちにとってもうれしい言葉ですね。
「周囲がしっかりと意見を伝えてくれて、自分とコミュニケーションを取ってくれたことがとても大きな財産になっていると思います」

見る側も作る側も飽きないものを
──仕事を始めた最初の頃はその思いには至らず、もうちょっと自分が自分がみたいなことで作っていた時もありましたか?
「もちろんそういう時期もありました。この本には初期のお仕事も掲載されていますが、最初の頃は被写体ともほとんどコミュニケーションを取らずに、カメラ機材のギミックに凝ったり、美術を過度に盛り込むことで、無意識に自分らしい世界観を強調しようとしていました。2017年に出版した『君の住む街』という写真集があって。東京の街と、そこで生きる女優さんを撮る雑誌連載35回分をまとめた本なのですが、最初の数回を撮った段階で、どの回の写真も似ているように感じてしまって。被写体のかたは毎回違うのに、写真から醸し出される様相が似ている。なぜだろうと考えると、それぞれの被写体の個性をよく見られていないのではないか、という結論に至って、そのことに気付いてからは、被写体の過去のインタビューを読んだり、その人が出演している作品を観たりするようにしました。現場でも撮る前に、コンセプトや撮影意図はもちろん、なぜそのかたを撮りたいと思ったのかなども、言葉にして伝えるようにすると、積極的にこちらの意図を理解しようと歩み寄ってもらえるようになったんです。そうやって相互理解の循環が生まれると、写真もその被写体である必然性を感じるものになったし、僕にしか見せてくれない表情や様相を撮れるようになった気がしました。それは必ずしもリラックスして自然体で笑っているみたいなことではなくて、どんな表情だとしても、信頼関係がちゃんと映り込んでいたり、その被写体と僕という、双方がその個々人でないと撮れない個性的なものになっていったという意味です。
それ以降、被写体ごとに撮影スタイルを変えるようになりました。着ぐるみの中に入るようなイメージで、その人の目から世界を見ようとすると、どう向き合えば、どう伝えれば自分の意図が相手に届くのかが分かってくる。相手の立場に立つこととか、それを受けて自分がどう思い、どう考えているのかをしっかり相手に伝わるように伝えること。それが創作の基本なんだということに初めて気が付いたんです」

──自分だけのものづくりをやり尽くして、連載中に目覚めたわけですね。
「キャリアの初期、最初の3年間ぐらいは世界中のフィルムを買って試してみたり、フィルムを燃やして、砕いて、刻んで、またコラージュしたり、カメラの中にゴミや粉末を入れてみたりして、あらゆる実験を試していました。それはそれで実りある試行錯誤だったと思います。けれどそういった技術面における工夫だけでは描けるものは限られていて、次第に飽きてしまう感覚がありました。見る人の記憶や心に残り続けるものって、やっぱり人と人が向き合って“人間”を描いた創作だと思うんです。人間同士が浸食し合って、反射させ合って作られたものにしか宿らない、人間らしい“矛盾”みたいなものがあって、そういったものにこそ、みる人は自己を投影したり、違和感を抱いたり、感情移入したりするのだと思います。“人間”というこの世界で最大の矛盾をはらんでいるものに向き合うような創作を続けられれば、どこかで飽きてしまうとか、辞めたいみたいなことは起こらない気がしています。
技術的に高度で実験的な手法ばかりに取り組んでいた時期はたくさんの方に注意やお叱りもいただきました。誰もやったことのない未知の手法であるだけに自分でもどういう仕上がりになるのか明確には分からないこともありました。そういうチャレンジを一緒にして下さる心強い方々もいれば、叱ってくださるような方もいたり、そういうギリギリの世代や時代だったのかなとも思ったりします」

──もういいやと諦められるのではなく、叱ってくれてその後も仕事をご一緒してくれたわけですね。
「それこそ十年ぐらい前、雑誌やウェブマガジンでとにかくたくさん撮るようになっていった最初の頃は、撮影に慣れているわけでもないのに、週に7〜8件撮っていたので、もう生活もぐちゃぐちゃで、何もかもが追いつかず、いろいろなスタイリストさんやヘアメイクさん、編集さんに、毎回のように怒られていた気もします……」
──20代前半で毎回となるとなかなかしんどいですね。
「本当によく怒られていました。けれど先輩方の言葉は、勉強になることがとても多くて、いまの自分を作って下さっているのは、そういった言葉の一つ一つだったりもすると思います。なので、ギリギリそうやって厳しく言ってもらえる時代に仕事を始められて本当に良かったと思っています。今は社会全体に、強くは言えない風潮もある気がするので、そういった意味で大変な時代ではないでしょうか。経験のない人であっても、みんな自分自身で気付かないといけなかったりする」
──師匠に付いて厳しく言われることがなかった分、仕事を一緒にしてくれた方たちから教えてもらったわけですね。
「そうですね。特にこの本を見返すといろいろなことを思い出します。みなさん愛情をもって共に創作に取り組んで下さったことを、心から感謝しています」

「写真は言語に縛られない、言葉を超えていく力がある」
──今回アートディレクションを平林さんにお願いしたのは、奥山さんの希望ですか?
「そうですね。平林さんのデザインは、整然と機能的な側面を持ちながら、圧倒的に個性あるユーモアが共存している。一見無機質な中に、人間らしいかわいげが同居しているデザインが、平林さんの特徴の一つだと僕は思っいて、とても好きなんです。この写真集はアーカイブ的性質も持たせるべき本なので、情報が整頓されていたり、機能的でありたいと同時に、本としての佇まいにどこかかわいげや愛らしさのあるものにしたかったんです」
──アーカイブとしてのファイルぽっさやボックス感みたいなものも感じますね。
「タイトルの『BEST BEFORE』=賞味期限という製品的なコンセプトに対して、やり過ぎず、引き過ぎず、本らしいデザインから逸れずに個性的に落とし込めるのも平林さんしかいないのではないかと思いました。余談ですが、平林さんには、最初、アークティック・モンキーズがデビュー直後にレディング・フェスティバルのトリで演奏した時の映像をお送りして『こういう本にしたいです』と伝えました」
──わかるような、わからないような依頼……!
「デビュー当時のアークティック・モンキーズって、ほんとにガレージで音楽に熱狂していた子供たちがそのままステージに来ちゃったみたいな雰囲気があったんです。みんな家着みたいな服装だったし…。(笑)一見、肩の力が抜けてるように見えて、キレ味が尋常ではなくて……とにかく緩急があってカッコいいんですよ。衝動でやってるように見えて、絶妙なバランスでまとまっていて。あの突風みたいな状態って、きっとどのバンドも瞬間的にしか生み出せない最大風速なんだと思うんです。『そういう本を作れないでしょうか』って。平林さんは、取りあえず一回受け取ります、みたいな感じでした(笑)」

──でしょうね(笑)。写真の順番は奥山さんが決めたんですか?
「写真の配置やサイズ、流れも含めてレイアウトを一度自分で組んで、平林さんにお渡しました。その後、平林さんに仕上げの微調整をしていただきました」
──アーカイブ性を求めながらも案件ごとにまとめず、ひとつのシリーズが散りばめられていますが、編集方針はどういうものだったのですか?
「同じ写真であっても、シリーズとしてまとまって見るのと、間に他のシリーズの写真が混在した構成で見るのでは、その一枚の捉え方に大きな違いがあると思っています。せっかく12年間分のあらゆるジャンル、あらゆる時期の写真を1冊にまとめるのであれば、一枚一枚の写真が、それぞれ最初に発表された初出時の印象とは異なるものにできるといいな、と思いました。つまり、この本のこのレイアウトだからこそこう捉えられる、みたいに、新たな意味を各写真に持たせたかったんです」
──最初の方に話していただいた、余白の意味が生きてくるわけですね。
「一つの案件で撮られた複数枚の写真であっても一枚一枚独立した写真として捉えた上で、再構成してみたかったんです。シリーズごとにまとめてページ構成を組むのは、言葉、キーワードに起因したレイアウト作業なので、ある意味とても楽なんですよね。けれども、写真は言語に縛られない、言葉を超えていく観念的な力がある。レイアウトを組む時は、極力その力を信じたいんです。異なる時期に異なる目的で撮られた写真なのに、見開きで並べてみるとその当時とはまた別の意味を持ち始めることがあります。この見開きの構成じゃないと、この写真の魅力が伝わらないみたいなことも『BEST BEFORE』の中では起きていると思います。写真集は、流れや構成といった全体でもって作品のコンセプトを伝えるメディアだと思っているので、一枚で見るときの魅力と、見開きで見るときの魅力がまた異なって感じ取れるように構成されていてほしい。全体性に意義があると思っています」

──never young beachの写真がたくさん掲載されていて、ページをめくりながら、「ネバヤンの写真は印象に残るものが多いな」と思いながら見ていました。
「最初にお話ししたような、コミュニケーションの蓄積がそのまま写真なり映像なりに映るということを最も体現しているシリーズだと思います。メンバーと僕は友人関係でもあるので、撮影の時点で既に積み上げられてきたコミュニケーションが十分にあって、お互いに信頼関係をもって創作に臨めているのが大きいと思います。信頼の土壌の上で作っているので、きっと互いの個性を発揮できているからこそ、印象深いものになっているのだと思います」
never young beach「SURELY」Music Video(監督:奥山由之)
──仕事を振り返って印象的だった人はどなたですか?
「やっぱりスティーブン・ショアと対談できたのは夢のような時間でした。ショアのポートレイトを撮ろうとした時、後ろに彼の愛犬を2匹見かけたんです。その犬を1匹ずつ両脇に抱いてほしいと伝えたら、『いいよ』って。『うわぁ、スティーブン・ショアが僕のお願いによって、両脇に愛犬を抱えている……!』と、妙な高揚を覚えましたね。『これはすごい』と思いながら撮っていました」
──世界の写真史に残るレジェンドですからね。
「それから、米津玄師さんも印象的でした。『感電』のMVで初めてご一緒したのですが、一曲の中に膨大な思考と実践のレイヤーが重なっていて、創作へ懸ける思いに切実さと質量を感じましたし、米津さんもまた、それをしっかり言葉にして伝えてくれたんです。自分もその思いの強さに応えたいという気持ちで臨みましたから、結果的に、ものすごく純粋なものづくりを一緒にできた感覚がありました。米津さんは、言葉数は少なくても、誠実に対話をしてくれる印象があって、それが共に創作をする時に大きな手助けになりました」

──ふたりとも91年の早生まれで同い年ですよね。
「そうなんです。年齢が一緒なので、見てきたものが近かったり、キャリアのスタートも同じ時期だったりして。初めましてでもお互いを理解し合うことが自然にできた気がしています」
──なるほど。
米津玄師「感電」Music Video(監督:奥山由之)
「『感電』のMVはとても貴重な物作りだったと思います。アーティスト写真にしても、米津さんの曲作りへの思いを丁寧に伝えてもらえたので、被写体が米津さんで、撮り手が僕じゃないと成り立たない、オリジナリティのあるものになった気がします。そのプロセスの中で、米津さんの人への伝え方がとても素敵だと思いました。僕は誰かと話す時に、強くて含みのある一言だけでなく、その言葉に行き着く前後や背景についても全部説明してしまう癖があるのですが、米津さんは出来る限り言葉を尽くして話してくださる時もあれば、きっとあえて言葉数を減らしてこちらに想像の余白を与えて話しているような時もあって。それがとても魅力的でした」
──誰もができることじゃないですね。
「真摯なんだろうなって。取り繕っていたり、嘘があったりすると、説明する時の言葉に真実味が出なくなってしまう。けれど、真剣に打ち込めば打ち込むほど、例え少ない言葉数であっても的確な言葉選びになるんだろう、と思います」
──自分の中の思考がクリアになるまでやるっていうことなんでしょうね。
「そうだと思います。作り手として僕もこういう人でありたいな、と強く思った出会いでした」

奥山由之『BEST BEFORE』
アートディレクション/平林奈緒美
寄稿/伊藤貴弘(東京都写真美術館 学芸員)/河尻亨一(編集者)
発行/青幻舎
定価/¥8,800
Amazonでのご購入はこちらから
Photos:Satomi Yamauchi(Portraits) Interview & Text:Hiroyuki Yamaguchi Edit:Chiho Inoue
Profile