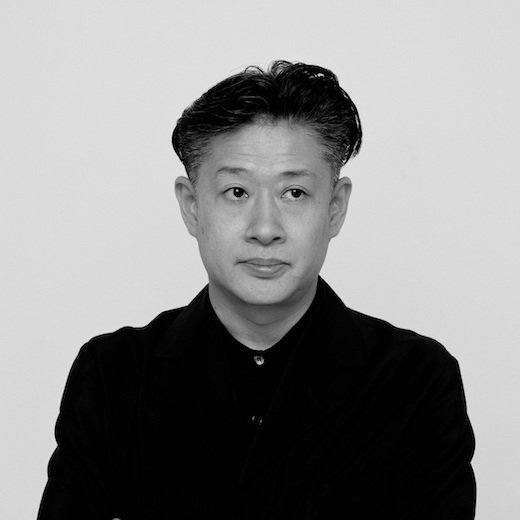世界で活躍する音楽家 三宅純に聞く、“映画のための音楽”とは

出版業界の裏で起きていたという前代未聞の実話を起点に、ストーリーをふくらませて生まれた驚くべきどんでん返しが連続するミステリー作品『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』。 ギル・エヴァンスを聴きながら脚本を仕上げたという、ジャズ好きのレジス・ロワンサル監督からの依頼で、このミステリーにスタイリッシュなまとまりを与えているのが三宅純氏のサウンドトラックだ。グローバルな活躍で世界から引っ張りだこの氏に、映画音楽のあり方をうかがった。

──この『9人の翻訳家』のサウンドトラックに限らず、三宅さんにとって2019年は蜷川実花監督の『人間失格』やNHKの『浮世の画家』のサウンドトラックを手がけられたり、勝沼恭子さんとのアルバム『COLOMENA』のリリースや東京でのコンサートと、非常にアウトプットの多い年だったのではないでしょうか?
「実際には『9人の翻訳家』の録音は昨年(2018年)に終わっていたのですが。そうですね、確かにアウトプットは多い年でした」
──この映画ではレジス・ロワンサル監督自身が脚本も手がけており、ギル・エヴァンスの「The Indivisualism(個性と発展)」を聴きながら脚本を書き上げたというエピソードをうかがいました。このお話は監督から三宅さんにも伝わっていたのでしょうか?
「ええ、最初の打ち合わせの際に聞きました。ギル・エヴァンスの中でもすでに具体的にこの感じというのが監督の頭にあって、メインテーマにしたいので、撮影に入る前に書いてほしいと言われました。実際にはよりシンフォニックにしたものを提案したところ、それを気に入ってくれました。冒頭に流れる曲ですね。ギル・エヴァンス風のモチーフという指定があった中で自分なりに多少抵抗してみたというかたちです」
──三宅さんにとってのギル・エヴァンスとは?
「ジャズ界、特にビッグバンド界においては、フランス近代に影響を受けた彼の和声の感覚というのは斬新でした。僕は10代から20代半ばまでジャズしか聴いていなかったたので、マイルス・デイビスとギル・エヴァンスのコラボレーションは、まさに青春のサウンドです」
──映画に登場する本の表紙のイメージではビル・エヴァンスのアルバムのジャケットの写真を使っていたりと、監督のジャズ好きの片鱗が伺えます。
「『アンダーカレント』(のジャケット)ですね。監督と最初に会ったときに彼がいかにジャズが好きかという話になって、当初は作業しやすいのではと思っていました。実際には幼少期のトラウマでサックス・セクションの音が生理的に受け入れないということがあったり、難しいこともありました」

──色やイメージもですが、音へのこだわりの強い監督という印象を受けました。
「こだわりの人ですね。そして迷う人でもありました。ある日の最後には『欲しかったのはこの音だ』と涙を浮かべてハグして別れたのが、翌日に会うと『やっぱり迷っている』というような(笑)」
──さまざまな映画監督とお仕事されていらっしゃいますが、監督によって音への注文の違いはありそうですね。
「そうですね。大枠だけ合意して、あとはあなたの最善を信じるので、好きにやって下さいというタイプの監督もいれば──(蜷川)実花さんやヴェンダース監督はそのタイプでした──、レジスのようにかなり細かい指定のある監督とがいますね」
──三宅さんの音楽で最も記名的といいますか、アーティストとしての特徴が出ているのはこの数年手がけていらっしゃる『Lost Memory Theatre』のシリーズかと思います。一連のアルバムの曲を聴いていると、まるで特定の時代や特定の場所が頭に浮かんできて、たとえインストゥルメンタルの曲でも登場人物が語りはじめるような印象を受けます。そういう意味ではとてもサウンドトラック的とも思えるのですが、三宅さんが実際に映画音楽のお仕事をされる時とは、どのような意識の違いがありますでしょうか?
「普通音楽を作る時はその音楽自体が主役ですが、映画音楽の場合、主体はあくまでも映像、演技、台詞にあるということが大きな違いです。どの角度からアプローチして、骨を抜くといいますか、主体にスペースを空けるということを意識しないと、全てを音楽で語ってしまおうとする傾向がありますから、そこには気を遣います」

──実は、三宅さんにこうしてお話を聞く機会を得たので、改めて音楽に耳を傾けるつもりで映画を観直していた際に、つい画面に意識がいってしまって、音を聴き逃してしまっていることが何度かありました。
「映画音楽としては、それこそが成功といえるのかもしれません。実は映画のラストシーンに僕のではない既存のトラックが流れるんです。このシーンは監督からの指示で5、6回書き直しをして、最後には涙を浮かべて『これが欲しかった』と言われたのにもかかわらず、また監督が迷ってボツに。その時は既に新曲を書くための時間が取れないタイミングになっていたので、やむをえず既存曲使用になりました。そのボツ曲はボーナストラックとしてサントラ盤に入ることになりましたのでぜひ聞いてみてください」
──話は逸れますが、先ほどのヴェンダース監督の『Pina(ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち)』で流れた「Lilies Of The Valley」は三宅さんの代表作のように知られることになりました。そもそもこの曲は映画よりもピナのダンスのために書かれたものだったのでしょうか?
「いえ、元々はダンスのためでさえありませんでした。2004年頃だったと思いますが、とある女性アーティストのために曲を書いてほしいという依頼があって、その中で生まれた曲なんです。ですが、デモを作っている最中にこの曲がアート・リンゼイの声で歌われるイメージが浮かんできてしまい、自分のアルバムに入れようと思って、プレゼンテーションの段階でこのデモを取り下げさせてもらったんですね。その後、ピナ・バウシュが来日した際、音楽監督がそのデモを気に入って持ち帰らせてほしいと言われました。後になってすでにピナの舞台でその曲を使っていると知らされました。それもデモの状態のまま――私のデモの中でも最も遠くまで旅をした曲になりました。結局、ヴェンダース作品にはにはそのデモをミックスをし直したものが使われ、当初のアイデアの通りにアート・リンゼイに歌ってもらったヴァージョン(「Alviverde」)は「Lost Memory Theatre」のシリーズの序章となったアルバム『Stolen from Strangers』の一曲目に入れました」

──最近の映画では冒頭からエンディングまで、音楽が必ずあって、音楽が映画の世界を包む役割を果たすこともあると思います。映画音楽を作る際はどのような意識で臨まれていますか。
「やはり映画は監督のものだと思うので、先ほど言った骨を抜くという作業をする中で、音楽がいかに色彩や空気感を与えられるかということをまず基本に考えます。小さい頃に映画音楽をまとめて聴いたことがあったんですが『こんなつまらないものを作るのだけはやめよう』と思った記憶があるんです──音楽単体では“骨抜きになってる”ということだったんですね。その問題意識は今もあって、あとで音だけ聴いた時にも音楽として成立していたいと思いますし、もちろん映画の作品性をあげるために存在していたいと思います」
──今回、フランス映画でのお仕事でしたが、三宅さんの音楽にとって、制作の場所としてパリという街はどのように機能していますか?
「実はパリが好きだったわけでも、パリを目指して来たわけでもなく、フランス語ができたわけでもなかったんです。国外に出ようという意識だけで、最後の最後に『じゃあ、パリ』と決めちゃったんです。利点としては、まず、ひきこもれる──かなり外界からの情報をカットできるという点があります。それでいてハブ都市としてさまざまなアーティストが通り過ぎていきますので、彼らとの交流だったりコラボレーションという意味においてはとても適した街だと思います。そして上を向いて歩いている限り、うっとりするくらいきれいな街です」
『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』
監督・脚本/レジス・ロワンサル
出演/ランベール・ウィルソン、オルガ・キュリレンコ、アレックス・ロウザー
音楽/三宅純
2020年1月24日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷シネクイント、新宿ピカデリーほか全国にて順次公開
gaga.ne.jp/9honyakuka/
配給: GAGA
© (2019) TRÉSOR FILMS – FRANCE 2 CINÉMA – MARS FILMS- WILD BUNCH –LES PRODUCTIONS DU TRÉSOR-ARTÉMIS PRODUCTIONS

映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』オリジナル・サウンドトラック
2020年1月24日(金) CD¥2,400(P-VINE RECORDS)
Interview & Text: Shoichi Kajino Edit: Sayaka Ito
Profile