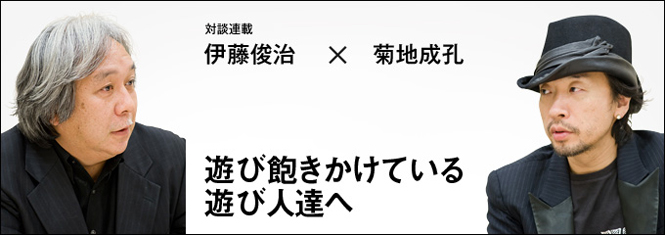パリは終わってしまったのか?[前編]/菊地成孔×伊藤俊治 対談連載 vol.1
vol.1 パリは終わってしまったのか?[前編]
カルチャー先進国として、かつて圧倒的な憧れの存在だった都市パリ。70、80、90年代を経て、インターネットの普及によって世界が均質化し、独特の文化のありがたみは失われてしまったのか? それでも、やっぱりパリの威光は健在なのか? そして、東京のオリジナリティは何処にいくのか?
![]()
消費されていくパリと東京のありがたみ
菊地成孔(以下K)「現在、雑誌業界に限らずとても不況である。そういう話になった時に真っ先に僕が考えたのが、『Numero』もそうなんですけど、パリに本体がある女性誌の日本版という雑誌を山ほど読んできましたが、Numeroは因みに“Japon”ではなく て“TOKYO”となっている。さほどの意味は無いと思いますが、直接都市と都市を結んでいると言える。遥か戦前から、つい最近に至るまで『VOGUE』や『FIGARO』を読むとパリがすごくありがたい感じがしたけど、今はそういった女性誌を読んでいても、パリと東京のありがたみというか、意味の違いがだいぶ出てきたという気がしていて。(伊藤)先生はパリガイドを書かれてましたよね」
伊藤俊治(以下I)「『トラベルス/パリ』という本で、『ラスト・タンゴ・イン・パリ』の舞台になったオルセー駅跡とか、ギマールのカステル・ベランジュ、ロースのトリスタン・ツァラ邸など、パリの20世紀建築を100件選んで、建築デザインに関しての解説を加えて書いたものです。この100年ほどのパリの建築の推多を見ると、本当にパリのシンボルというのが大きく変わってしまいましたね。透明化し、非物質化しているというか。パリという都市のイメージが成立しにくい」
K「なるほど。しかし伊藤先生の場合はアカデミックですし、アートですよね。女性文化風俗という意味では、例えば昔だと岸惠子さんみたいな方が、ぐっと最近になるとカヒミ・カリィさんみたいな方が、特派員のようなイメージで、パリの情報を教えてくれる。デザイナーや翻訳家といった人々もいましたが、とにかくアイコンのような人がいて、憧れと親近感を併せた視線で見られていた。今は登場している人たちがどのくらいパリにアイコンとして立っているのかもわからない。中山美穂さんは特派員的ではないし。そういう意味でも「パリの雑誌」という力が落ちてきている気がしますけど」
I「そうですね。最初はモード雑誌を輸入してて、やがては日本版が出て80年代に『marie claire』が人気を集めるようになった。僕も毎月コラムを書いていたけど、あれは日本版というより名物編集者の安原さんの独断的なパリ雑誌だった」
▶続きを読む