米国内の分断を描いた『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で注目を集めたアレックス・ガーランド監督の最新作『ウォーフェア 戦地最前線』が、1月16日に日本公開される。
本作でガーランド監督が徹底したのは、戦争を“ドラマ”として描かないこと。そのために、イラク戦争でネイビーシールズ隊員として従軍したレイ・メンドーサが共同監督・脚本をてがけ、自身の実体験をもとに戦場の時間と感覚を限りなく忠実に再現した。

作品の本公開に先駆け、青山学院大学 国際政治経済学部の学生15名が本作を鑑賞し、ジョセフ・クインが演じたサムのモデルになったジョー・ヒルデブランドとの対談とディスカッションを行った。戦争経験者が身近にいない世代の学生たちは、この映画をどう受け止めたのか。
想像していた戦争と、映像で体感する戦争の違い
本作の舞台は2006年のイラク。アメリカ軍特殊部隊8名の小隊が、最も危険な地域とされる街ラマディでアルカイダ幹部の監視任務に就いていた。彼らの予想に反して突如始まる襲撃。そこから描かれるのは、勝利や正義の瞬間ではなく、ただ「生き延びようとするだけの時間」だ。映画的な音楽や劇的な演出はほとんどない95分間。観客は兵士たちと同じ時間を共有し、状況を把握する冷静さと考える余裕を奪われていく。

今回、対談に参加したのは「いつか外交やビジネスなど国際的な仕事に就きたい」と志す、国際政治学科を専攻する学生たち。彼らが本作を鑑賞後に、口にしたのは「自分が想像していた戦争と、映像で体感した戦争はまったく違った」という感覚だった。これまで授業やニュース、映画を通じて触れてきた戦争は、一つの物語や情報として整理され、理解しやすい口調で語られてきた。しかし本作では、爆発後に突然訪れる耳鳴りのような沈黙、銃声と叫び声が入り混じる混乱、視界も思考も奪われる戦地の“ノイズ”そのものが描かれる。
学生の一人はこう語る。「なかなか過ぎていかない時間の長さと緊張感が、兵士たちが置かれている極限状態を疑似体験させる装置のように感じました」さらに「これまで文章や言葉で戦争を知ったつもりでいましたが、映像として体験すると、想像の限界を超えた苦しさと恐怖がありました」というコメントも。戦争が“理解できる出来事”から、“身体で感じてしまう体験”や“死を予感すること”へと変わった瞬間だったという。

退役軍人が率直に語った、軍人としての勤めと戦争の虚しさ
対談の中でまずあがった質問は「自身の経験と、映画の内容に相違はあるか」という問いだった。それに対し、ジョー・ヒルデブランドは「95%は正確です。残りの5%は、実体験を映像として成立させるための調整のようなもの。自分たちが経験したことを忠実に描くことで、観る人が戦場を追体験できるようにしたかった」と答えた。
この言葉に、学生たちは驚きつつ、納得している様子だった。それは決して誇張ではなく、「作品が観ている側が消耗するほどリアルだった」からだ。
さらにジョー・ヒルデブランドが語ったのは、この作品が誕生した理由。「脚を失う大怪我をした戦友のエリオットは、19年経ったいまも戦地で自分の身に何が起きたのか記憶にありません。映像化して戦地で何が起こり、どうしてこういう状況になったかを彼に見せてあげたいという気持ちで作った作品でもあります。戦地から戻って兵士たちが語り合う機会はありませんでした。その間、個々が抱えた重荷から解放されるためにも、もう一度痛みを経験してでも作る価値があった作品です」

他にも「日本は徴兵がなく、国のために戦う感覚が正直わからない」という、率直な問いも学生から投げかけられた。それに対して答えはこうだった。「羊と狼、そしてシェパード犬を想像してください。私は自分を皆さんの平穏な生活を守る“シェパード犬”だと思っています。戦場で考えていたのは、国の理念よりも、目の前の仲間を守ることでした」
学生たちもまた、兵士を“英雄”としてではなく、「国から目的を果たすために派遣され、極限状況に置かれた一人の人間」として捉え直したという。「戦場では、どんなに優秀な軍人でも自分と仲間の命を守ることで精一杯。一人の人間に戦争全体をどうこうできる余裕なんてないと感じました」
それから、イラク戦争はイラクに大量破壊兵器があることを大義に始まった。実際はそのような兵器は見つからず、いまだに侵攻についての批判が止まない。その点を尋ねると、ジョー・ヒルデブランドは「不幸なことに、侵攻を判断するのは軍の上層部であり政府。我々には判断ができない領域です。それに完璧な政府は存在しません。もちろん、より良い政府にするために選挙に参加し投票を行います。批判があったことは知っているものの、実際に下された判断を覆すことはできません。なので政府や軍を指揮する人にもこの作品を観てほしいです。実際の戦地がどれほど醜く、過酷で、個人的なものだと伝えたい」と語った。

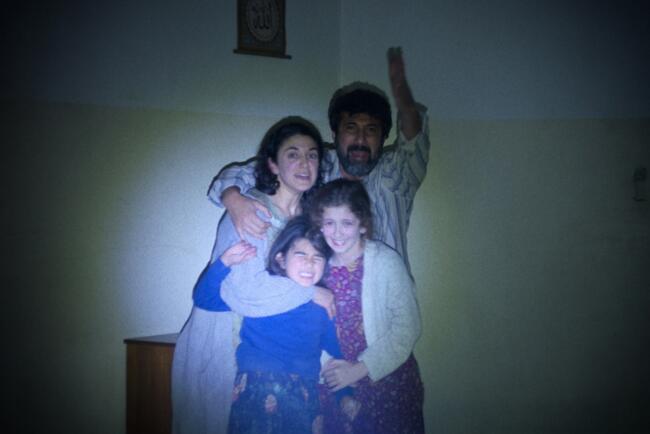
また、数人の学生が語った印象的だった場面がある。映画終盤に瓦礫の中からイラク兵たちが静かに姿を現すシーンだった。激しい戦闘のあとに訪れる、不自然なほどの静けさ。勝利でも、解放でもない、ただ人がそこに立っている光景だ。「戦争が終わったというより、ただ戦争が米兵と共に現れて、米兵と共に去っていったように感じました」戦争は始まりよりも、終わったあとの方が重い空気が漂う。その現実が、強く胸に残ったという。
授業で学ぶ戦争と、現場の戦争のあいだ
国際政治学部の授業では、戦争が起こる理由や政策決定のプロセスを学ぶという。しかし、実際に現場で何が起きているのか、兵士ひとりひとりがどんな状態に置かれているのかは、ほとんど知り得ない。
「これまでに鑑賞した戦争映画は市民目線のものが多数だった。そういう意味でも、この映画を観ることは新たな視点を学べるので意義深いこと」
「現実を知らなければ、戦争や政策について語ることが空虚になってしまう気がしました」
「戦争を“知ったつもり”になっていたことに気づいた」
そんな意見もあり、この映画は、理論と現実のあいだにある大きな隔たりを、学生たちに突きつけた。『ウォーフェア 戦地最前線』は、戦争を止める答えを示す作品ではない。しかし、戦争がどれほど個人的な体験であり、人間同士が起こす出来事でありながらいかに残酷であるかを、観る者に示している。

最後にウクライナとロシア、イスラエル・パレスチナ間のガザ紛争、タイとカンボジア、米国とベネズエラなど、昨今増え続けている戦争について、ジョー・ヒルデブランドはこう語る。
「悲しい現実だが、自分が生きている間に戦争がなかったことは一度もなかった。戦争は醜いもので、どんな形を取ってでも止めるべき。戦争以外の選択を模索するべきだと強く思っています。一方で日本の学生たちが口々に『日本は平和だ』と言えることは本当に素晴らしいこと。その裏で戦う兵士がいることも覚えていてもらえたらと思います」
平和な日本に生きる私たちが、戦争を遠い出来事にしないために。この映画は、考え語り続けるためのきっかけとなるはずだ。
『ウォーフェア 戦地最前線』
2006年、イラク。監督を務めたメンドーサが所属していたアメリカ特殊部隊の小隊8名は、危険地帯ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務についていた。ところが事態を察知した敵兵から先制攻撃を受け、突如全面衝突が始まる。反乱勢力に完全包囲され、負傷者が続出。救助を要請するが、さらなる攻撃を受け現場は地獄と化す。混乱の中、本部との通信を閉ざした通信兵・メンドーサ、指揮官のエリックは部隊への指示を完全に放棄し、皆から信頼される狙撃手のエリオット(愛称:ブージャー・ブー(鼻くそブーの意))は爆撃により意識を失ってしまう。痛みに耐えきれず叫び声を上げる者、鎮痛剤のモルヒネを打ち間違える者、持ち場を守らずパニックに陥る者。彼らは、逃げ場のないウォーフェア(=戦闘)から、いかにして脱出するのか。
脚本・監督/アレックス・ガーランド、レイ・メンドーサ
出演/ディファラオ・ウン=ア=タイ、ウィル・ポールター、ジョセフ・クイン、コズモ・ジャーヴィス、チャールズ・メルトン
配給/ハピネットファントム・スタジオ
© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
2026年1月16日 (金) TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開
https://a24jp.com/films/warfare/
Text:Aika Kawada Edit:Chiho Inoue






