TOGA古田泰子インタビュー「マイノリティで悩んでいる人たちの味方でありたい」
1997年にデザイナー古田泰子が立ち上げた「TOGA(トーガ)」も四半世紀を迎えた。パリ、ロンドンと発表の場を移し、さらにコロナパンデミックを経て変化してきたブランドのあり方と変わらない服作りへの思い。そして、いま次の世代へとつなぐトーガの未来への旅が始まる。(『ヌメロ・トウキョウ(Numero TOKYO)』2023年6月号掲載)

半年先の未来を見据えた服作り
──トーガの原点とは?
「私にとって洋服は、幼少期から一番手っ取り早くなりたい自分になれる手段でした。10代の頃は学校内の基準値や多数派に合うかどうかが外見で判断されることが多く、そこに馴染めなかった自分をアピールするためのアイデンティティでした。だから常に着る人の心の支えになる、身に纏うことで自信を持って前に出ていけるよう後押しする服というのが根底にあります」
──そのためにどんな服作りをしてきたのでしょうか。
「便利だとか、着やすそうという褒め言葉より、ここぞというときに着たいと選ばれる服でありたい。奇をてらうわけではないけど、雑誌に載っても目に留まるような見たことのない服を作ってきました。一時ブームになったノームコアにはあまり興味がありません」
──ノームコアが流行ったり、コロナ禍ではリラックスしたホームウェアのような服が増えましたが、世の中の潮流はどう受け止めていますか。
「ファッションは基本的には時代の表象であるべきだと思っているので、全く無視して作れるものではありません。だからといって流れに乗るのはデザイナーの仕事とはいえない。真剣に半年先の未来を予測して、その先に何が足りないのかということをずっと考えています」
23年春夏「SKIN, UNDERWEAR, SPACIOUS」。男女同じ条件で着用して胸がギリギリ隠れる、深く開いたVが象徴的なアイテムは、女性のニップレスに対する不平等へのトーガ流の問題提起でもある。そこに揺れたり、体から離れたときのリズムによる楽しさを組み合わせた。
──どのように読み解いているのですか。
「情報源は新聞です。特に紙のほうがよく、土曜日は新聞を読むことを習慣にしています。ネットだとどうしても興味のあるものばかり見てしまうので、興味のあるなしにかかわらず目を通したい。あと見かけたら「ビッグイシュー」(ホームレスの社会的自立支援のために発行されている新聞)も買うし、フリーペーパーも手に取ります。不特定多数の人たちに向けて発信されている情報は絶対に社会を無視していないので学びがあります」
──社会情勢を知らずに服は作れませんよね。
「ファッションにまつわる情報は、MD的なアイデアソースにはなりますが、メッセージにはなりません。紙媒体世代なので情報は紙から得て、言葉に引っ張られ、興味を持ってさらに調べる。それが全然苦ではなく面白い作業なんです。若い世代からしたら、ネットでも同じことをやってるよといわれるかもしれませんが、得ようとしている情報がすぐ上がってくるネットとはなんか違う。新聞には雑多に情報が詰まっていて、例えば戦争の話題の下には、老害の本の新刊案内、次のページには読者からの投稿があるというように社会の縮図のようです」

写真家Valeria HerklotzとスタイリストEliza Conlonによる初のロンドン撮影を行った23春夏のPULLA(写真右)とVIRILIS(写真左)のルック。
──コレクションを作るにあたってアイデアの出発点は? シーズンのキーワードやテーマはどのように生まれるのでしょう。
「考えていると、言葉が降りてくるんです。それをノートに記しては見直して、頭の中でぐるぐる考えていくうちに、啓示じゃないですが、これは必要ないと感じる瞬間や、もう少しこっち方面で掘り下げてみようとか閃く。その先は、イメージが広がるかどうか。最終的には何か解き放つことがあって発表しますが、服の表現方法が毎回ガラッと変わるかというと、人生の中の数年を切り取っているだけで、そんなに簡単に変わるはずはなく。ただ対外的には言葉の説明があったほうが説得力につながるので、プレスリリースを書く作業を通じて、もう一度整理しています。
テーマに掲げた3ワードは、古田のマントラといわれたりしますが、あながち間違っていません。日本人的な自分の感覚は、物事を白黒、善悪だけで判断できないので、着地点は決して一つではなく、受け取る側にも言葉から想像してもらうのが楽しい。たとえばインドに旅行して、今シーズンのテーマはインドです、といったわかりやすい手法は自分には合っていないと思います」
新たなセッションがグローバルな強さを生む

──2023年春夏は、女流写真家の山沢栄子さんの作品にインスパイアされています。
「2019年に大きな回顧展があり、そこで初めて1930年代から活動していた女性写真家で、実験的かつ抽象的な写真を撮る人がいたと知り驚きました。後にコロナ禍でショーを中止し、リモートで発表する状況の中、以前から注目していたクリエイティブディレクターのヨップ・ヴァン・ベネコムと仕事をすることになり、彼から『女性の素晴らしさや優秀さを感じている』という内容の文章が送られてきました。
一方で、ジェンダーや社会的マイノリティの問題が可視化されるようになり、女性写真家のパイオニアである山沢さんにとっての現代と、いま私がいる現代を重ね合わせることで、女性のつながりを表現したいと思ったんです。音楽は現代音楽家の石橋英子さんに依頼し、石橋さんの現代的でクリーンだけれど歪みを感じる音と山沢さんの写真のイメージが結びつき、ヨップの言葉も加わって連鎖していきました」

『BUTT』『the gentlewoman』を手がけるアートディレクターJop van Bennekomが選出した、オランダ出身のLiv Liberg(上)、韓国出身のNina Ahn、NY出身でLAを拠点に活躍するZoё Ghertner(左下)、パリ拠点のフランス人Camille Vivier(右下)が撮り下ろした2023年春夏イメージ。
──ヨップさんに注目するようになったきっかけは?
「最初に彼の存在を知ったのは、十数年前にLAのインディーの本屋で見た『BUTT』という雑誌です。すごい名前の雑誌だと思って中を見ると、安い紙質や印刷なのに、美しい写真とレイアウトが印象的で、その後、東京のアートブックのイベントでも見かけて思い出しました。また別のタイミングで、雑誌『ザ・ジェントルウーマン』をいいなと思っていたら、同じ人が手がけていると知り、さらに興味が湧きました。その頃、トーガとしてシーズンイメージをこれまでの女性像をもとに、もっと国籍、文化、性別を超えて視野を広げていきたいというタイミングだったのもあり、6年前に初めてコンタクトして、ようやく21年春夏に実現しました」
──新たなセッションによって、どんな変化が生まれましたか。
「一歩踏み出して外を見てみると、ジェントルな視点でもの作りのできる優秀な人たちが、世界にはたくさんいました。性的な偏見に敏感であり、信頼し合ってフラットな目線で一つのものを作り上げている。それまではスタイリングも自分たちでやっていましたが、18年春夏からスタイリストに入ってもらっています。違う視点が入ったことで、よりグローバルな強さが生まれたと思います。コロナ禍でヨップと組んで、映像形態で発表したときも、ヴィヴィアン・サッセン、アンダース・エドストローム、ジョニー・デュフォートと、前からやりたかった人とセッションでき、すごく楽しかったんです。現地に行ってはいないけど自由を感じました」
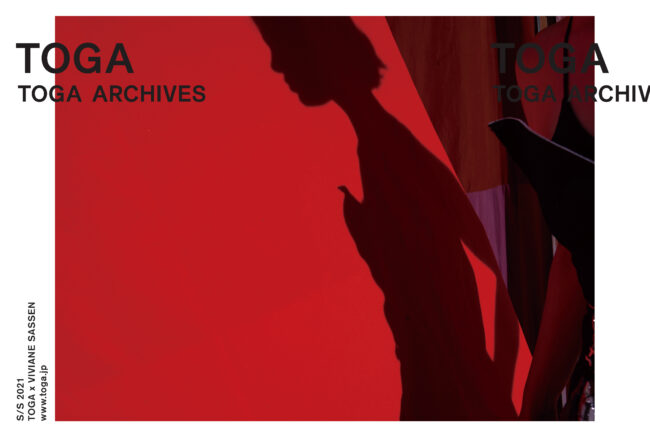

21年秋冬「SIMPLIFY, EXPAND, FLATTEN 」。画家、五木田智央の絵に着想を得たコレクション。Director & Camera:Anders Edstrom

──さかのぼりますが、07年にパリに進出し、14年にロンドンに発表の場を移したことはある種の挑戦だったように思います。
「パリでの発表は資金面でショーを継続していくことの限界に直面しましたが、ショールームはずっと続けていました。そんなとき靴のデザインを評価していただき、ヨーロッパで靴を作ってみないかと勧められた先がイギリスの会社でした。最初は数型からスタートしましたが、この靴メーカーのショールームが世界中で展開されていたこともあり、靴デザイナーでもないのに靴が広まり、靴から服を知る人も増え、ブランドの認知度が格段に上がったんです。そこで、再びショーをやってみたいと思い、組んだアタッシュ・ド・プレスがロンドン拠点だったので、心機一転ロンドンで発表することにしました」
──ロンドンとの相性はどうでしたか。
「サポートしようという意識の強いPRと、靴を作っているイギリスのオフィスのおかげで、イギリスにもトーガのスタッフがいるような頼もしい状況を築けたのは大きかった。大勢の人になんとなく好かれるよりも、トーガに強い愛を持ってくれる人を3人にすることのほうが大事だと知りました」
子どもたちの未来に向けてメッセージを発信し続ける

──この先もロンドンで発表し続けるのでしょうか。
「時代って移り変わるんですよね。私がロンドンに移動した当時は、ロンドンのファッションウィークに勢いがありましたが、コロナ禍を経て縮小傾向になってしまいました。いま全力でロンドンでショーを行うことへの疑問と、せっかく自由な発表方法を得たのに、すぐにヨーロッパ主体の、特別な人たちだけを招待するシステムに戻ることにも疑問を感じています。一度始めたら、また続けなくてはならないし、冷静に見ると、今は締めていたものがバーンって弾けてお祭り騒ぎのような印象です。果たして本当にそこで発表したいのか、そこに行かなきゃという波には飲まれたくないという思いがあって足踏みしている状態です」
──確かにコロナ禍はファッション業界のあり方を考えさせる大きなきっかけでした。では古田さん自身の人生のターニングポイントとして出産による変化はありましたか。
「出産しても一度も休むことなく発表していたので、やっていることは大きく変わっていませんが、強いて言えば時間の使い方。スパッと切り替えられる力はつきました。そして、子どもたちの未来についても考えるようになりました」
──未来に対して、社会にとってどんなブランドであるべきだと?
「私の子はまだ服に全く興味はないけど、今の10代の子たちが、ファッションに興味を持ち始めるタイミングはやって来るはずだから、それがどんな方向性だとしても、お金を払ってでも欲しいと思うのはどんな服かなと考えます。買い物を一つの投票のように捉えると、やっぱり企業理念みたいな哲学なのではないかと。高校生になる友人の子も、地球環境のことを考え、自分の意見もしっかりしています。だから、デザインがいいというだけでなく、この会社の取り組みに共感できる、ここならお金を落としたいという意思がはっきりある。私たちも曖昧に流すのではなく、きちんとメッセージを伝えることが重要です」
──時代の先を読みつつ、発信するトーガのメッセージとは?
「例えば、7年前、20周年の18年春夏には、男性と女性のモデルを起用し、男性に女性ものを着せたり性別の垣根を取り払いました。今後もLGBTQ全てに対して、マイノリティで悩んでいる人たちの味方でありたい。さらに今季からは、TOGA TOO(トゥー)というジェンダーを気にせず着られるラインを始めました。特に男性の中には女性ものの売り場で買うのが恥ずかしいという方もいるので、気兼ねせず買えるよう、どちらかというと男性をちょっと解放したいと考えました」
──衣服ロスや環境問題も無視できません。その点は今後どう取り組んでいくのでしょう。
「26年たって、世代を超えて親子で買いに来たり、自分の着なくなったものを娘に着せたりというお客さまもいます。だからトーガ専門買取店をやりたいとずっと考えています。もともと古着を扱っているので、穴があいていたら補修し、ボタンを付け直すといったリメイクのノウハウがあるので、強みを生かして、古いものでも手のかけ方次第でもう一度価値を与えられる仕組みを確立したいと社内で相談しているところです」
──持ち主や時代が変わってもトーガの服を愛してもらえますね。
「新しいコレクションだけでなく、26年間の歴史の全て、愛情と時間をかけて作ってきたので、どれも思い入れがあります。それを自分たちの手でまた蘇らせたいのです」
23年秋冬「REVEAL, INSIDE, LIBERATION」。ロンドンにてプレゼンテーション形式で発表。
──トーガがこれから向かう先は?
「発表形態自体も当たり前のことを当たり前とせず、考えて提示し、しっかりメッセージを発信する。ジェンダーについても、一過性のファッションとして捉えられないように継続的に発言していくことが役割だと感じています。思っている以上に、悩み苦しんでいる人は世界中に大勢います。数シーズン、モデルをミックスして発表したところで、問題がなくなるとは思いません。同性の親が子どもを連れてきても居心地のいいお店だったり、そういった事実を隠さなくてもいい未来のことまで考えて行動していきたいですね」
──最後に、最近、影響を受けた作品や人物はいますか。
「今すごくずっと一緒に組みたいと思っているのが、フランスの女性映画監督のセリーヌ・シアマ。完全にシアマ中毒です。映画『燃ゆる女の肖像』を見たとき、今まで見た中で全てを塗り替え、一番好きな作品になりました。女性二人が主役で、メインキャストに男性が登場せずとも成り立っていて、何も起こらない。映像も美しいし無駄に音楽も使わない、繊細でありながらメッセージは強い。それに、シアマと出演女優のアデル・エネルは元パートナーで、デモに参加したりと隠さずに活動をしている姿勢も共感できます。私もこのままでもいいんだと感じさせる力があるんです」
──これからのトーガの方向性にリンクする作家ですね。
「いつかセッションしたい方です。彼女だったらトーガをどう表現してくれるのだろうと、わがまますぎる想像をしています」
Photos:Kiyotaka Hamamura Interview & Text:Masumi Sasaki Edit:Masumi Sasaki, Chiho Inoue
Profile





















