近年、「SRHR」という言葉を耳にする機会が増えてきた。とはいえ、その意味や重要性を実感として捉えられる人は多くない。産婦人科医であり、SRHRのまつわる活動を行う池田裕美枝医師に、心と体と生き方の関係を見つめ直すうえで欠かせないSRHRについて聞いた。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2026年1・2月合併号掲載)

SRHRとは?
「『性と生殖に関する健康と権利』のこと。全ての人が、性や生殖に関して正しい情報を得て、自分らしい人生や性を謳歌できるように自分の意思で決定できること、そして、それを権利として社会が応援する考え方ともいえます。例えば、いつ子どもを産むか、誰と関係を持ち、どんな人生を歩むかは、どこに住み、どんな仕事をするのかと同じくらい人生に大きな影響を与えるファクターです。自分らしい選択をするためにも、性の多様性や性的指向の違いを理解し、生殖器の仕組み、妊娠のメカニズム、病気の予防について正しく知ることが重要です」
日本で浸透しにくいのはなぜ?
「1948年、日本では戦後の人口急増を抑えるために『優生保護法』が制定され、世界に先駆けて、人工妊娠中絶や不妊手術が一定の条件下で合法化されました。その根底には優生思想的な発想があり、障害や病気を理由にした強制不妊手術も行われていました。『産む・産まない』という選択が女性の権利の保証ではなく、社会や経済の都合で制度化された経緯があるのです。
1996年に『母体保護法』へ改正され、優生的な文言は削除されたものの、人権としての議論は十分に根付いていません。一方、欧米では市民運動を経て1970年代に中絶が合法化。そこでSRHRの理念が形成され、中絶や避妊の選択が人権と結びついています。例えば、フランスでは全ての人に平等に中絶の権利を保障しているため、無料で中絶ができたり、避妊具の無償配布、経口中絶薬の普及が進み、社会的支援を含めた包括的な体制が整っています」
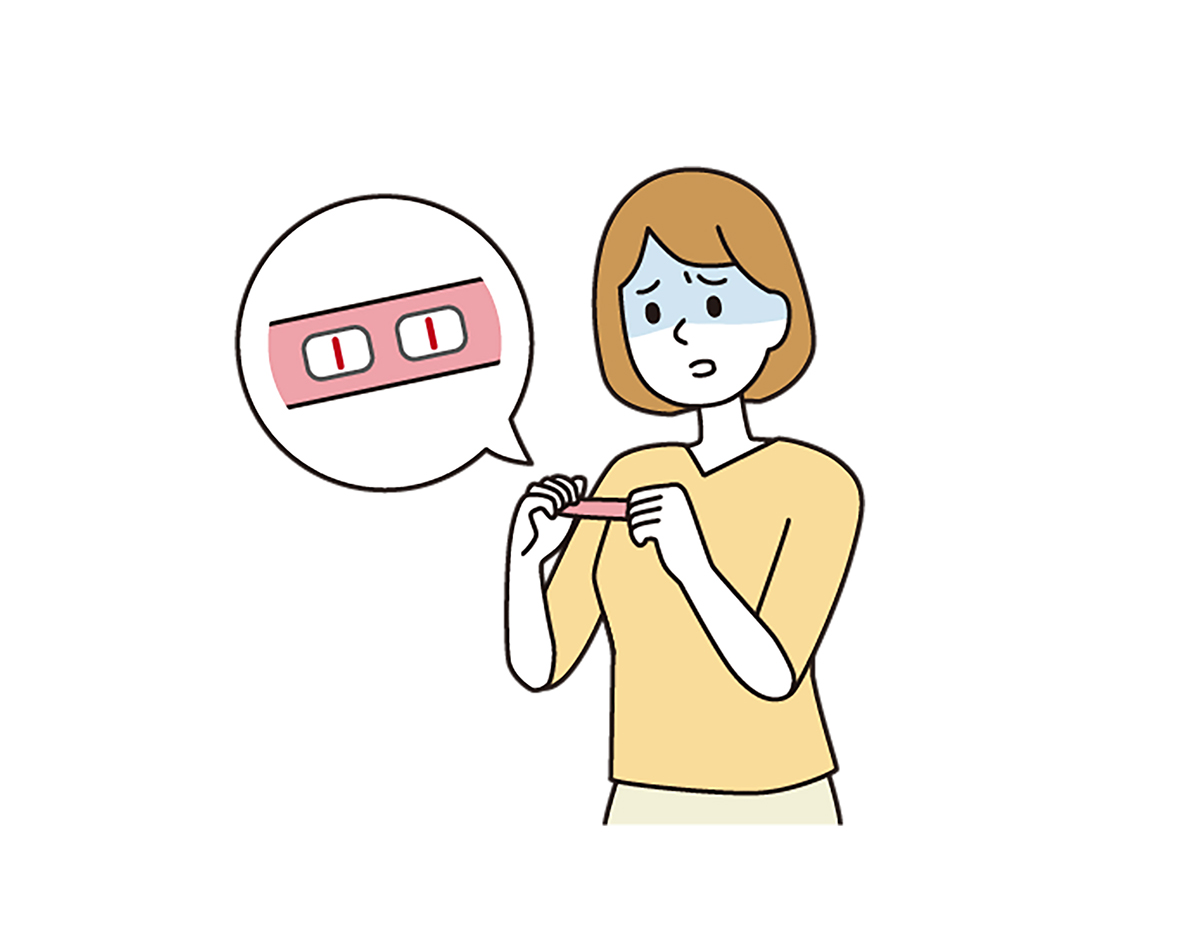
日本の課題は?
「『産む前の心と体』『産まない選択』への支援が十分でなく、結果として望まない妊娠や、心や体の不安や不調を抱えている人が多いこと。欧米では看護師やカウンセラーが常駐するユースクリニックが設置されている国が多くあり、避妊・性感染症・メンタルヘルスまで包括的に支援しています。また、月経や避妊をコントロールできる手段がたくさんあり、学生や低所得者なら無料でそれらを得られます。日本では手に入る手段が極端に少なく、高額でアクセスも良くない。心と体の悩み、避妊についてなど気軽に相談できるところが少なく、問題が深刻化してから医療機関を訪れる人が後を絶たない現状を変えることが課題です」
性と生の権利を守るために必要なこと
「『体の自己決定権(ボディリー・オートノミー)』の考え方がもっと浸透するといいのかなと思いますが、まだ十分に理解されていません。日本で『自己決定』というと『自己責任』に近いニュアンスで受け取られがちで、選択の結果は全て自分で背負うものと考えられてしまいます。でもSRHRの根底にあるのは、頭で決めるのではなく、心と体の声に耳を澄ませ、その反応を尊重するという姿勢です。日本社会は『個』よりも人との関係性を重んじる文化があります。相手に期待される自分でいようとしたり、場の空気を読むことで自分を抑えてしまうことも多い。そうした文化の中に、欧米的なボディリー・オートノミーをそのまま持ち込んでも浸透しにくい。だからこそ、性や心、体について語る機会を増やし、自分の感覚を言葉にする練習が必要だと思います。
相手の意向に流されるのではなく、『私は今、どう感じているか』を確かめる。怖い、嫌だと感じたら、そのサインを押し殺さない。これは性行為の同意だけでなく、避妊や医療の選択、出産、終末期まであらゆる場面に関わります。パートナーとのコミュニケーションに不安があるとしたら、最初からセックスや避妊の話題を出さずとも、『最近ちょっと体調が変わった気がする』といった体の話から共有するだけでもいいと思います。そこから『このタイミングで避妊に気をつけたい』とか自然に話を広げられたら。そんなふうに小さな対話の積み重ねが、ボディリー・オートノミーを育てる第一歩になると思います」
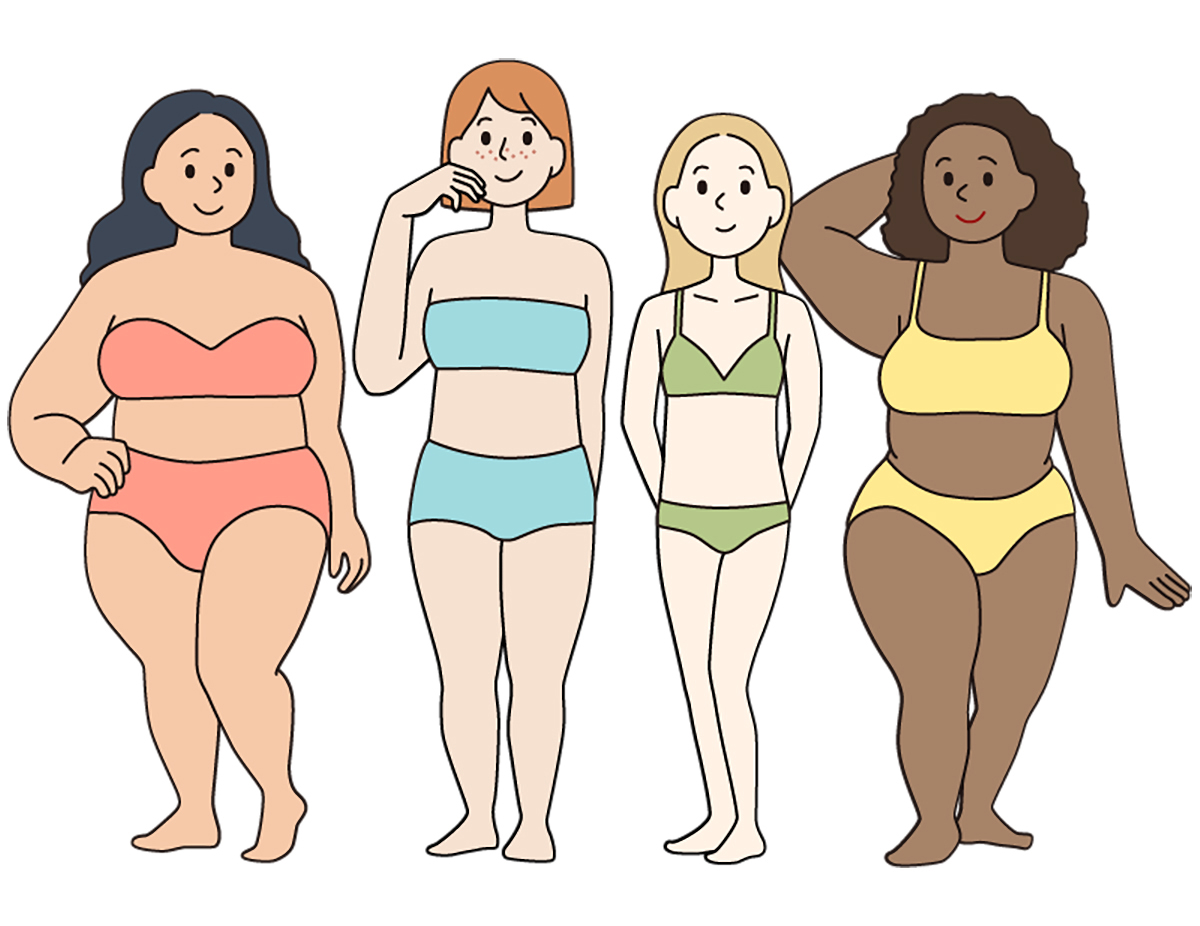
知る力を養うために
「性について正しい知識を得られるサービスが増えているので、ぜひ活用してみてください。例えば日本産婦人科学会が運営する『女性の健康推進室 ヘルスケアラボ』『ピルコンU30のためのメール相談』、こども家庭庁の『はじめよう プレコンセプションケア』など。病院に行く前に悩みを打ち明けられるツールはとても便利ですが、大切なのはどのサービスを使うかではなく、それをきっかけに自分とどう向き合うか。また、必要なときに身近な友人や家族に話したり、かかりつけ医に相談するなど、『受援力(じゅえんりょく)』=人に助けを求める力を持つことも大切だと感じます」
Edit & Text:Mariko Uramoto






