「おしゃれしたい!」という気持ちはどこから? 着飾ることの意義とは。東京大学での特別講義をまとめた『東大ファッション論集中講義』が話題の神戸大学大学院・平芳裕子教授にインタビュー。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2025年11月号掲載)

──着飾りたいという欲望は歴史上いつ生まれた感情なのでしょうか?
「服は耐久性が低い素材でできているので実証は難しいのですが、歴史をさかのぼれば、先史時代には動物の皮を身に纏っていたり、洞窟壁画を描くための顔料で身体をボディアートのように装飾したりしていたともいわれています。もちろん身体を保護するためという可能性もありますが、ほぼ裸で森に暮らす人々も存在しますので、単なる実用性のみで服が扱われてきたとは考えにくい。それでは、なぜ人間は服を必要とするのか。理由は他者と自分を差別化し、集団生活で人間関係を構築する人間特有の習性にあります。
例えば、西洋では上流階級が高価なものを身に着けて階級社会を形成しました。つまり社会の発展に欠かせない役割を服は担ってきたのです。それは『着飾る』の定義にも関係します。『着る』と『飾る』に言葉を分解したとき、一般的に『着る』は機能性、『飾る』は装飾を加えていくことがイメージされます。でも、どこからが『着る』で『飾る』になるのかの基準は誰にも決められません。それは結局、他者との比較によって生まれるものだから。例えばTシャツを着ている人の横に裸の人がいたら、Tシャツさえも装飾品になるかもしれない。状況や関係性によって『着る』と『飾る』の境界線は移ろい、逆説的にいうと常に人類は着飾ってきたのです」


──日本の服飾はどのように発展したのでしょうか。
「日本では洋装化が始まった明治時代以降にジュエリーなどの装飾品も身に着けるようになりましたが、それ以前は、着物が親しまれ、四季折々の色彩と紋様を楽しんでいました。江戸時代には公家・武家・町人など身分によって服装が異なっており、贅沢を禁じる法令がたびたび出されましたが、着飾りたいという気持ちがなかったかというと、そうではないと思います。許される範囲のオシャレとして、布地を豊かに用いる着物文化が育まれてきました。そしてその美意識は、今の日本を代表するようなファッションデザイナーが、ジュエリーなしで成立する服そのものの強さを表現してきたことにつながっているのかもしれません」
──社交場も着飾る意識を醸成させた重要な環境ではないでしょうか。
「そうですね。ただ、日本では、明治時代に外国からの客人をもてなす場として『鹿鳴館』が建設されましたが、短命に終わっています。上流階級の女性の外出が制限されていたなか、急に華やかなドレスを着ることに加えて、ダンスをすることに抵抗があったのだと思います。そうした風土に馴染まなかった背景もあり、日本では伝統的な着物に対し、西洋のファッションは毎年スタイルを変える軽薄なものとして捉えられてきたように感じます。でも、本来ファッションは、社会の中で個性を自由に表現する文化として尊重されるべきもの。洋装化が始まって150年がたつ今だからこそ、日本社会全体でも考え方をアップデートしていく時代に突入しているのではないでしょうか」
──現代において「着飾る」ことが社会や人類にもたらす影響とは?
正直なところ、SNSで手軽に自己表現できる今、以前に比べて社会におけるファッションの役割はパワーダウンしているように感じます。でもだからこそ、本当の自分を取り戻す手段として着飾ることが大切なのではないかと思います。店頭で手に取ったり、美術館で見たり、リアルな身体感覚として自分の気持ちが上がってパワーを得られるような服に出会ってほしい。各々が自分らしく着飾ることができるようになれば、多様性に富み、もっと個人が輝ける社会になるはずです。
もう一つ、現代的な機能性重視の観点からすると、ファッションは否定されてしまうときもありますが、ファッションにとってみれば実は纏うべき人間の身体から解放されたときこそアートになり得るのではないかと思うんです。つまり、動くことのできない構造の服や何も入らないミニバッグまで、機能性から見ると不思議なデザインがたくさんありますよね。でも役に立つことから解放されて、非常に面白いデザインだったり、素晴らしい装飾だったり、そういうものが人間のイマジネーションをかき立て、時代を飛躍させてきたのではないでしょうか。それこそがファッション独自の力だと信じています」
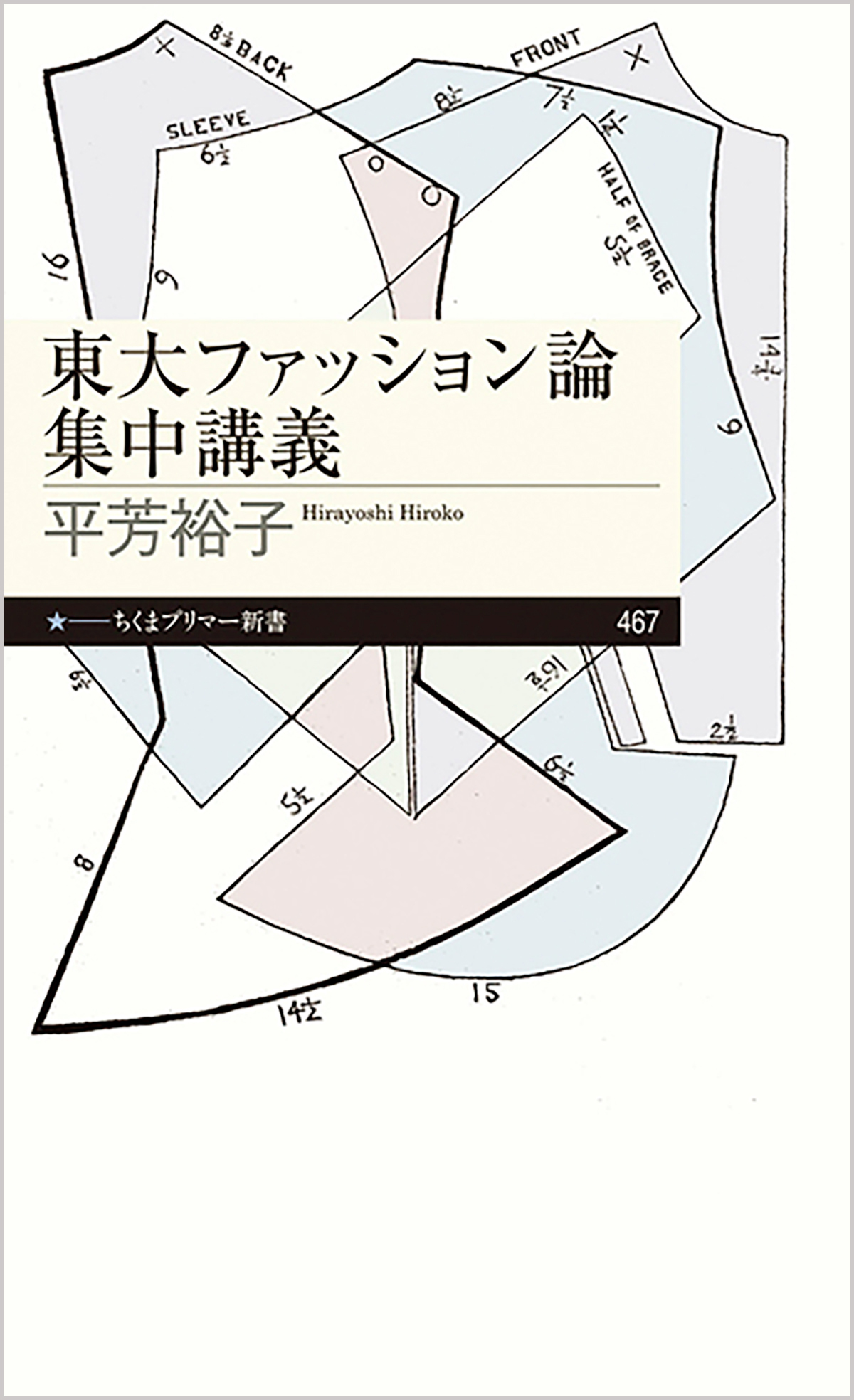
『東大ファッション論集中講義』
著者/平芳 裕子
価格/¥990
発行/ちくまプリマー新書
ファッションとは何か? 衣服とは? 12のテーマを通じて文化や芸術としてのファッションを学び、歴史と未来に問う。東大生の反響を呼んだ一度きりの特別講義をまとめた一冊。
Interview & Text:Yoshiko Kurata Edit:Mariko Kimbara








