西洋でも日本でもない独自のポジショニングと、文理融合的なアプローチの服づくりで異彩を放つ「テルマ(TELMA)」。シャツ、ジャケットなどの定番的アイテムを得意とするが、その背後には膨大なイメージやテクノロジーを血肉としたストーリーが流れていて、それを表現するために驚くほどの手間がかけられていることを、パッと見ただけで知ることはできない。デビューから3年、2025-26年秋冬のキーアイテムを通して、知られざるこだわりと制作のプロセスをデザイナーの中島輝道に聞いた。

──TELMAの服には、意表を突くような素材感やディテールの妙がありますね。実際に手に取って着てみないとわからない。
「ありがとうございます。私の場合、ファッションから入っていないというのが強みになっているかもしれません。もともとファッションブランドをやりたいというよりも、新しいモノ、コトを生み出したい気持ちが先にありました」
──ブランド名のTELMA(テルマ)とは?
「私の名前が輝道(てるまさ)で、幼少期からの愛称です。ブランドをやることに対して責任を持たなきゃいけないという覚悟から、自分の名前をつけました。ただ、自分を打ち出したいわけではないので、ニックネームを採用した感じです。ニックネームは親しい間柄じゃないと呼び合わないですよね。なので、親しみやすく寄り添ってもらえるような存在でありたいという願いも込めて」
アントワープを拠点に向き合った西洋の服づくり
2025SSコレクションより。
──TELMA 立ち上げまでのキャリアについて、改めて教えてください。
「大学ではプロダクトデザインを専攻し、主に家具をメインにプロダクトのデザインを学びました。祖父が数寄屋建築の設計士で、日本的な採光性のある家屋に住んでいたので、幼少期の経験もベースにあると思います。ファッションに進むと決めてからは、アントワープ王立芸術アカデミーに進学。卒業後はドリス・ヴァン・ノッテン、その後イッセイ ミヤケで経験を積みました」
──和洋折衷的なものづくりのスタイルは、2つのメゾンを通して培われた?
「そうですね。まず、その前に受けたアントワープの教育の影響も大きいと思います。本当にいろんな学生がいて、トップメゾンの別注が並ぶようなお店で自分も別注をつくっていた裕福なクラスメートとか、一方では本当に情報が乏しい地域から来た人もいて、でも彼らのつくる服には彼らにしかできない強さがある。そんな環境の中、あなたは何ができるの?というのをひたすら問われる4年間でした。自分の好きなものはぼんやりとありましたが、それだと全然ダメで、もっと論理的に向き合わないと自分の形にできないと気づかされました」

──ドリス・ヴァン・ノッテンではどんなことを学びましたか。
「女性像を表現するには、ものすごい量の素材が必要だということです。たとえばジェーン・バーキンにもいろんな文脈があって、イギリス人だけどフランスで活躍したこと、トレンチだけじゃなくて、カーキのパンツ、デニム、オーバーサイズなど彼女にしかできない着こなしをしていましたし、人の佇まいとマインドはひとつの生地では表現できない」
──ドリスはとりわけ女性像の創出がうまかった?
「アントワープ勢って、いい意味でメゾンが多くあるパリに対して田舎なので、パリとは異なる独自の価値観があり、常に自分たちの私小説みたいなところをやっている。パリのメゾンにはミューズがいますが、アントワープのデザイナーは毎回新しい女性像を描き出してストーリーをつくります。ドリスは特に、クリエイションの真ん中に人がいるのかいないのかというところを、徹底的に考えていたデザイナーだと思います。革小物を売らず、服で勝負してきたブランドですから。実際の服づくりの部分では、体型を選ばない服のつくり方、分量の持たせ方など、多くを学びました」
西洋はムード、日本はモノ。その間で生まれる服
2025AWコレクションより。
──その後、イッセイ ミヤケに入ったのはどんな経緯で?
「いろんな学びを得た結果、やはり生まれ育った日本の文化伝統を吸収しない限り、西洋のデザイナーとは肩を並べるところまで辿り着けないと思ったからです。イースト・ミーツ・ウエストみたいなところをやっていきたい」
──戦略的帰国だったのですね。では、イッセイで学んだことは?
「まず、生地を知らなすぎると怒られました。イッセイ ミヤケは糸からつくる会社なので、全国の職人さんに会いに行くところから経験させてもらったことが、今のTELMAのものづくりにもつながっています。特に惹かれたのは、東北の手仕事でした。東北は環境が厳しくて、麻しか栽培できない。でも麻は薄いし肌触りはゴリゴリするし、やっぱり寒い。じゃあ重ねて刺繍で留めてみようっていうシンプルな発想から、刺し子、裂織り、こぎん刺しなどの技法が生まれました。すごく納得する部分があり、そういう人間の知恵には興味が掻き立てられます」
鉄のプリント、ハイテク刺繍、平面ジャケット
──コレクションはいつもどのように組み立てるのですか。
「最初にインスピレーションがあって、そこから連想した要素をどんどん集めていきます。今シーズンの入り口は、都会の夜でした。仕事で終電を逃して表参道を歩いていた時、ちょうどイルミネーションのシーズンで、人がまったくいなくて、でも街は整備されていてウィンドウが煌々と光っていて。すごく気持ち悪いなと思うと同時に高揚感もあった。未知のものに遭遇すると、戸惑いながらもワクワクしますよね。そういうクリーピーだけどワクワクする感覚を呼び覚ますようなコレクションをつくりたいと思いました」
左:ショーの演出のためにパーティのデコレーション用モールで制作したアクセサリー(非売品)。右:スタイリングのポイントになっていたビジュー付きロンググローブ。Numero CLOSETにて販売予定。
──ムードボードには、いろんなイメージが集まっていますね。
「星空、アール・ヌーヴォー、『アダムス・ファミリー』、『銀河鉄道999』、『かいじゅうたちのいるところ』、カート・コバーンのグランジもあります。すべて夜をテーマに集めたものです。ただ、それだけだと服はつくれないので、集めたものを因数分解して、いろんなスタイルやテクニックも取り入れて、自分なりの新しい夜を想像/創造していきます」
──たとえばアール・ヌーヴォーだと、どのような服への落とし込みになるのでしょうか。
「アール・ヌーヴォーは1920年代、初めて鉄やガラスが造形に使われた芸術運動でした。技術がひとつの価値観を広げて、新しい芸術を生み出したんです。そういう本当に新しいものをつくってみたい。ちょうど新しいプリントを探していた時期だったので、鉄のような新しい質感のプリントをやってみようとなりました」
アール・ヌーヴォーの植物モチーフを鉄をイメージした質感で表現した立体的なプリント。左のミニドレスは、NumeroCLOSEにて販売。
──鉄のプリント。遠目には箔プリントに見えますが、よく見ると硬質で立体的です。
「生地の上に鉄がのっているイメージで、滋賀の染め工場で施した発泡プリントに京都の箔プリントをのせ2種類の技法を組み合わせています」
誰も見たことのないものを生み出すために

──TELMAにとって、日本の伝統技法は欠かせないものになっていますか。
「そうですね。ただ、職人さんの技術をそのまま取り入れるのではなくて、その技術をベースにしながらも、まったく違う印象になるところまで持って行くということを大事にしています。それが僕なりの職人さんたちへのリスペクトであり、恩返しかなと思うので。逆に職人さんが「やりたくない」といったらそれまでです。TELMAを立ち上げて以来、ずっとご一緒している職人さんの工場が3、4軒ほどあって、シーズンによってさらに加わることもあります」
──職人さんと一緒にチャレンジをする上で、何が大事だと思いますか。
「やっぱりコミュニケーションではないでしょうか。何回も通い詰めて、自分でも試作してみたものを持参して初めて、だったらこうしたほうがいいのでは?と会話が生まれることがあります。最終的には、ほらできたよ、すごいだろ、となる」
左:チェーン刺繍、スパンコール刺繍など様々な手法の刺繍を用いて立体化した星モチーフが印象的なミニドレス(NumeroCLOSEにて販売)
──中長期的な取り組みもありますか。
「あります。たとえば刺繍の量産化です。西洋で刺繍といえばクチュールの世界のものであり、それはそれですばらしい文化なのですが、日本で同じことをやろうとしても意味がない。日本はハイテクが得意なので、テクノロジーを活用すれば、量産も可能になり、素晴らしい刺繍の価値を多くの人に伝えられるはず。そこを狙って続けているシリーズがあって、今シーズンでいうと、星のモチーフが該当します」
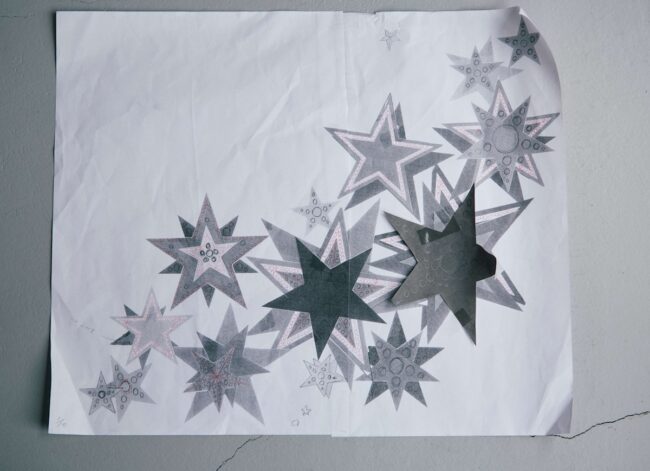
──星のモチーフは、アップリケだと思っていました。
「アップリケを重ねているように見えますが、チェーン刺繍、スパンコール刺繍など、すべてデータでプログラミングされていて、機械でやっています。刺繍は平面の生地をデザインするのが通常ですが、もっとアクセサリーっぽく、刺繍を超立体化するというのをやりたかったんです。設計図を描いて、そこに手刺繍も組み込み桐生にある老舗の工場でつくりました」
──まさに設計の世界ですね。ちょっと難解でわからないですが、直感的に面白く見えます。
「まさに、僕がつくりたいのは衝動に訴えかける服。そのためには生産背景からリデザインしなければいけないと思っています」
ワードローブの可能性を広げるジャケット

──プロセス的に今回、最も大変だったピースは?
「製品プリントのジャケットですね。今回、日本独特の雰囲気を出したくて、新しいカタチと向き合いました。まず、パターンをフラットになるように引いて、脇下は開けた状態で半分だけ縫製。別の工場に移して、フラットに潰した状態で両面プリントしました。そうすることで、プリントがのるところ、のらないところができて、同時にプレスで折り目もつけられるんです。その後、再び縫製工場に戻して、縫製し直して、肩パットを入れて、裏地をつけて完成」

──手間がすごい(笑)。
「着物的な服ですが、実際に着ると立体的になります。これを成立させるカギとなるのが折り目で、キャラクターを最も生かすために、糸からつくりました。本当にわずかな違いで、硬さも立体感も変わりますから。こういう仕事が今できるのは、おそらく日本だけではないかと」
──このショッキングピンクが、プリントとは思いませんでした。
「クリーピーですよね。染めではなくプリントなので水を使わなくていいというメリットもあります。ピンクジャケットの素材はリサイクルポリエステルですが、ファーストルックに出した黒のジャケットのほうはシルクウールです。シルクウールは折り目が残らないので、一度生地を樹脂に浸す加工を施してから縫製しています。そのあとの工程は同じ。シルクウールは、横ハリがあるぶん、その反発感が美しいんです。実際に着た時、その感覚の違いを楽しんでもらえたらなと思います」

──不思議な場所に、モノクロのプリントが組み込まれています。
「ファーの毛並みを自分で描いた絵をプリントしています。夜といえばイブニングの装い、つまりエレガントなムードですが、そこも新たに崩したい思いから、コミカルなファーの線画に辿り着きました。都会の夜の光を彷彿とさせるパステルカラーの線描で塗りつぶされた無地をつくろうというアイデアです。最終的には『アダムス・ファミリー』のイメージで、モノクロにしました」
──面白いですね。突飛な着地でびっくりしますが、アイデアの軸にブレがないので説得力があります。
「西洋って、ムードをつくるのがうまい。日本はやっぱりモノなんです。どちらがいい悪いではなく、それぞれに特性としてあって、TELMAはちょうどその間をいきたい。西洋のブランドでもなく、日本のブランドでもない、その中間を目指しています」
──人に寄り添う服をつくりたいというTELMAの思いが、話を伺うほど味わい深く伝わってきました。時間をかけて楽しみたい服ですね。
「そうなれたら嬉しいです。すぐに受け入れられる服というよりも、クローゼットにあって捨てられない服でありたい。1年後インナーで着て、2年後にアウターに出して、3年後に柄同士のセットアップにするとか。そういう体験を提案したいですし、誰かの行動を少しでも変えることができたら、それがTELMAの価値じゃないかなと思っています。プリントはタイムレスですし、着るのに勇気のいる色を使っているのもそういうメッセージを込めています」
Photos:Ai Miwa Interview&Text:Miwa Goroku Edit:Masumi Sasaki























